同じクラスだったワシントン大学からの留学生が「まりはいつも色々な色の服を着るから」と、くれたネックレス。
またもや、思い出話になってしまうんですが・・・
2002年から2007年の間にフランスをふらふらしていた。
それまで、海外に出たのは、小さい時に親に連れられて1ヶ月パリに滞在したことがあるだけで、日本を出て本格的に、たったひとりで「暮らす」ということをしたことはなかった。 出国カウントダウンが始まると、毎日「鬼平犯科帳」を読み(いまでも愛読)、フランスで豆腐を手に入れるルートを探したりしていた。自分がこんなに日本文化を愛していたのか、と驚き、こんなんでフランスに行ってどうするんじゃ、と、完全にヴォワイヤージュ・ブルー(?)だった。
母国から切り離されている、という不安は、海外に住んでみたことがある人にしかわからない。
旅行であれば、とりあえず帰る日にちが決まっているのだから、「やっぱなんとなく落ち着かない」ぐらいの気持ちで済む。けれど、いつ帰るのか、というより、帰るのかどうかさえもわからない場合、慢性的な不安と孤独というのはどうしても存在の底に抱えなければならない。
言葉が通じない不安とか、家族と離れている不安とは違う。 物理的に、生まれ育った土地と切り離されている、という不安。
土地が繋がっているところから来た場合は、やや軽減されるかもしれない。でも、海を越えて来た人にとって、「地面が変わる」というのは、思った以上に大きくのしかかる。 見かけが違うということが、こんなにも人を不安にさせるのか、と初めてモンペリエの街に降り立った時に思い知った。
それまでの私は、人と同じ、というのがまるで自分の存在を丸ごとかき消されるような気がして恐ろしく、同年代の女の子たちが、同じような格好で同じような髪型で同じようなブランドのバッグを持ち同じような曲を聴き同じような雑誌を読んでいるのが理解できず、だからといって特別オリジナリティがあるわけでもないから、その狭間でもがもがともがいていた。
その自分が、同じような人がいないといって不安がっているのに、面食らってしまった。 留学生活での人間関係は本当に繊細だ。同国人がいれば、その人と。そうでなければ、見かけの似ているアジア人同士がなんとなくグループを作る(留学先の言葉の習得レベルが低ければ、その傾向は顕著になる)。一匹狼もいるけれど、完全に孤立を守り続けるなら、そのうち心身に故障を来す。
そうは言っても、せっかく遠くまで来ているというのに、見かけが変わり映えのない、たどたどしい会話のメンツに囲まれて、安心はするけれど「これでいいのか」という気にもなってくる。ネイティブと話したり、自国にいたら出会うことのない国の子たち(アジア人同士だって、本当はそうなんだけれど)と交流しないのは「逃げている」という気にもなる。同族嫌悪も出て来る。そういう中で、ひりひりしながら暮らす。それでも、彼ら、彼女らが褐色の目と黄色の肌を持っていることに、どれだけほっとしたことか。どれだけその存在に感謝したことか。
語学学校の最初の年、私は自分の習得レベルが低いのに、はったりが上手かったので、自分の本当のレベルよりも大分上のクラスに入れられてしまった。それで、仕様がないから、オプションで選択した演劇のクラスの子たちと仲良くなって、彼ら彼女らから吸収することにした(みんな本当にいい「先生」だった)。名前も覚え易かったのか、やたら顔が広くなった。でも、やっぱり怖いから、演劇で一緒だった韓国人、中国人の子と仲良くしていた。
ある日の授業で、歴史の話題になった時に、クラスでほとんど交流をしない韓国人の女の子(いつも一緒にいる子とは別の子)が、激した様子で私ともう一人の日本人にこう言った。 「私の祖母は、従軍慰安婦にされて日本人から酷い目にあった。だから、私は日本人を絶対に許さない。日本人なんかとは、絶対に仲良くしたくない。」 その時は、先生があわてて話題を変えてうやむやにしてしまったのだけれど、私は衝撃を受けた。テレビや教科書でしか出て来ない話題としか思っていなかった私たちを、彼女は明らかに「当事者」として捉え、露骨に憎しみをぶつけてきたのだから。
後で、友達の韓国人の子が、「あんな風に思っている子は稀だから、気にしないで。」と慰めに来たけれど、釈然としなかった。私は何もやっていないのに。言葉を交わす前から憎まれてしまう、日本人に生まれただけで、私という個人の存在を否定されてしまう、なんてことは、26年生きて来て一度もなかった。 いま、愛国教育を受けて洗脳されているとメディアは盛んに言うけれど、教育による刷り込みだけで、あそこまで憎しみを強くできるだろうか、と思う。まるで、生まれてからずっと磨いて来た鉛玉のように、彼女の憎しみは鈍く強く光っていた。あの問題が、全て本当だったかどうか私たちは真実を知らされていないし、女の子の銅像の前で金切り声をあげている人が、果たして本当に被害者かどうかもわからない。けれど、どのような経緯にせよ本当に酷い目にあった人はいて、その人が恨みや悲しみを込めて辛かった記憶を繰り返し繰り返し聞かせることで、あの彼女のように、憎しみを受け継ぐ人がいるのだ、ということを、私たちは受け止めなくちゃいけないと思う。
おせっかいで優しいフランス人や何かの縁で出会った色々な国の人たちが誘ってくれて、出不精のわたしも、数々のパーティーや、イベントや、お茶や、スポーツや、散歩や、飲み会に参加した。底抜けに楽しくて、バカバカしくて、気持ち良かった。
だけど、どんな時も、ふと、「ああ、この人たちは、本当にいい人たちだけれど、人種が違うんだな。」という現実を実感する瞬間があった。私は別段、国粋主義でもないし、一緒にいた人たちが差別的な言動をしたわけでもないのだけれど、ふいにどうしようもない郷愁にかられることがあった。
もちろん、差別的な発言をなんの躊躇もなくする人もたくさんいた。街を歩いていると、ガラの悪いちんぴらに「ニーハオ」と声をかけられたりする。自分の目を引っ張ってつり目にしたりする。そこまであからさまでないにしても、自分の言動が誰かを傷つけていると気づいていない人は多い。
ナント大学で勉強していた頃、生活費を稼ぐのにいくつかアルバイトをしていた。たまたま下宿先が18世紀に立てられた歴史的建造物のアパルトマンで、そこそこのお金持ちや弁護士の事務所が入っている建物だった。その一階に住む老夫婦の家の掃除に通っていた。
そこのおじいちゃんは、昔海軍にいた人で、背が高くかくしゃくとしていて、頭も良い人だった。色々な格言を教えて貰った。息子さんたちはよその県にいたので、私を半ば孫のようにかわいがってくれていた。 そんな人でさえも、わたしに「まりは色が白いね。中国人なんかとは違ってきれいだね。」と言ったりした。 「中国人なんか」という一言に傷ついた。褒めてくれるならその比較は要らないのに、と悲しくなった。言っている本人は、褒めているつもりだから差別発言だなんてこれっぽっちも思っていない。日本を直接差別してないのだから、別にいいだろうと思っていたりする。あれだけ知性のある人でさえも。
私が出会って来た中国人たち、韓国人たちの顔が浮かんで来る。鼻持ちならないことを言う人もたまにはいたけれど、みんな目的を達成しようと一生懸命生きていた。少なくとも「敵」ではなかったし、これからも「敵」になってはならない。
今日の朝日新聞で、村上春樹が領土問題に付いて寄稿している。その中で、領土を巡って熱狂するのは「安酒の酔いに似て」いて、そういう安酒をほいほい振る舞う論客に、私たちは注意しなければならない、と書いていた。はっとしたのは、領土を問題にしたプロパガンダはヒトラーのやり口である、という所だった。
国境線というものが存在する以上、残念ながら(というべきだろう)領土問題は避けて通れないイシューである。しかしそれは実務的に解決可能な案件であるはずだし、また実務的に解決可能な案件でなくてはならないと考えている。領土問題が実務課題であることを超えて、「国民感情」の領域に踏み込んでくると、それは往々にして出口のない、危険な状況を出現させることになる。それは安酒の酔いに似ている。安酒はほんの数杯で人を酔っ払わせ、頭に血を上らせる。人々の声は大きくなり、その行動は粗暴になる。論理は単純化され、自己反復的になる。しかし賑(にぎ)やかに騒いだあと、夜が明けてみれば、あとに残るのはいやな頭痛だけだ。(中略) 一九三〇年代にアドルフ・ヒトラーが政権の基礎を固めたのも、第一次大戦によって失われた領土の回復を一貫してその政策の根幹に置いたからだった。それがどのような結果をもたらしたか、我々は知っている。今回の尖閣諸島問題においても、状況がこのように深刻な段階まで推し進められた要因は、両方の側で後日冷静に検証されなくてはならないだろう。政治家や論客は威勢のよい言葉を並べて人々を煽るだけですむが、実際に傷つくのは現場に立たされた個々の人間なのだ。
(リンクは朝日新聞デジタルの会員登録で読めます。多くの人に読んで欲しい。無料会員だとアーカイブが読めなくなるので、図書館にでも紙面を見に行って下さい。) 今、自国を離れてどこかの国に暮らしている日本・中国・韓国人たちは、毎日本当に神経をすり減らしていると思う。自分たちには全く落ち度がないのに、一部の政治家たちの自己顕示のための煽動に、神経をすり減らさなければならないなんて、つらいだろう。
村上さんの言うように、「報復だけは絶対にしてはいけない」です。





 J12 (←フラ語で「あと12日」、の意。)
カオスよりこんにちは。
もう、なにがなんだか。引越しはイルネギーがえる。
J12 (←フラ語で「あと12日」、の意。)
カオスよりこんにちは。
もう、なにがなんだか。引越しはイルネギーがえる。


 ナントで日本人女子学生が意識不明の重体で発見されるという事件があった。
直接の面識はないけれど、同じ日本人として大きな衝撃だった。
ナントで日本人女子学生が意識不明の重体で発見されるという事件があった。
直接の面識はないけれど、同じ日本人として大きな衝撃だった。
 じゃあ~ん。
やっと新しい洗濯機がやってきました。
長かったコインランドリー生活(帰国までかと覚悟していたのですが)に終止符。
(洗濯機騒動記は
じゃあ~ん。
やっと新しい洗濯機がやってきました。
長かったコインランドリー生活(帰国までかと覚悟していたのですが)に終止符。
(洗濯機騒動記は 「おあずけ」
さすがは不条理の国、ラヴ・ランジュ(lave-linge、洗濯機。こちらは男性名詞。。。)ひとつとってもつっこみどころ満載です。
きみにはドゥ・ミニュット(2min.)という名をしんぜよう。
あと1ヶ月よろしく。
ところで、ラファ、ローラン・ギャロス3連覇ですねー。
すごいなぁ。
フェデラーの200km/hを超えるエースとか、スライスの巧さに前半は結構危うい気がしましたが、後半はいつもどおりどっしり。
彼の2本のヴィッテルの置き方とか、コートに入ったら右側のラインだけ足で均して、靴下を直し、ラケットで踵を叩き、頬にかかる髪を耳にかけるという手順を崩さないところが、
「おあずけ」
さすがは不条理の国、ラヴ・ランジュ(lave-linge、洗濯機。こちらは男性名詞。。。)ひとつとってもつっこみどころ満載です。
きみにはドゥ・ミニュット(2min.)という名をしんぜよう。
あと1ヶ月よろしく。
ところで、ラファ、ローラン・ギャロス3連覇ですねー。
すごいなぁ。
フェデラーの200km/hを超えるエースとか、スライスの巧さに前半は結構危うい気がしましたが、後半はいつもどおりどっしり。
彼の2本のヴィッテルの置き方とか、コートに入ったら右側のラインだけ足で均して、靴下を直し、ラケットで踵を叩き、頬にかかる髪を耳にかけるという手順を崩さないところが、

 23時に近くなって、ようやく空の蒼が黒に包まれる。
ノヴァク、残念だったね・・・怖い顔ばっかりのナダルに比べると彼は表情豊かで「かあいかった」です。勝者はミスをしませんね、ほんと。
23時に近くなって、ようやく空の蒼が黒に包まれる。
ノヴァク、残念だったね・・・怖い顔ばっかりのナダルに比べると彼は表情豊かで「かあいかった」です。勝者はミスをしませんね、ほんと。
 エリック・ロメールといえば、
愛とモラルに関する薀蓄を語るモラルゼロのヒーローと、彼を取り巻く女たちの矛盾した言動を、赤と白と青で彩る映像。
素人っぽさを徹底的に好むシネアストだから、主人公もなんだかふわふわひょろりとした人が多くてあんまり私は彼の映画のヒーローたちって好きではないのだけれど、さすがはジャン=クロード・ブリアリ、こんなにどっしりリアリスティックにふわふわスケベオヤジを演じられる人は少ない。
エリック・ロメールといえば、
愛とモラルに関する薀蓄を語るモラルゼロのヒーローと、彼を取り巻く女たちの矛盾した言動を、赤と白と青で彩る映像。
素人っぽさを徹底的に好むシネアストだから、主人公もなんだかふわふわひょろりとした人が多くてあんまり私は彼の映画のヒーローたちって好きではないのだけれど、さすがはジャン=クロード・ブリアリ、こんなにどっしりリアリスティックにふわふわスケベオヤジを演じられる人は少ない。

 mel, mellis > Miel。はちみつはラテン語でメル。フラ語でミエル。
はちみつ好き。たぶん1ヶ月に一瓶開けている。
Comme un certain W (ou P) ? 某熊のWさん(Pさん)並み。
料理に使うので減りが早いのかもしれない。
一番好きな蜂蜜は、ナントから電車で行かなければならない小さな町の市場で売っているそうなので(頂き物)、たぶんもうお目にかかれまい・・・と、空瓶を眺めてためいき。
気を取り直して最近は写真のものを買っています。なんでもないMiel de Fleursだけれど、濃厚でいて味は結構あっさり。和風の味付けにもなじむオリコウサン。
さて、今日は蜂蜜の話でなく。
mel, mellis > Miel。はちみつはラテン語でメル。フラ語でミエル。
はちみつ好き。たぶん1ヶ月に一瓶開けている。
Comme un certain W (ou P) ? 某熊のWさん(Pさん)並み。
料理に使うので減りが早いのかもしれない。
一番好きな蜂蜜は、ナントから電車で行かなければならない小さな町の市場で売っているそうなので(頂き物)、たぶんもうお目にかかれまい・・・と、空瓶を眺めてためいき。
気を取り直して最近は写真のものを買っています。なんでもないMiel de Fleursだけれど、濃厚でいて味は結構あっさり。和風の味付けにもなじむオリコウサン。
さて、今日は蜂蜜の話でなく。
 Une signe de vie...(いきてます。)
ジャン=クロード・ブリアリが逝ってしまわれた・・・。
Une femme est une femmeを思い出しました。
なんだか、かっこよかった時代の人々がこぞっていなくなってしまうのに、
あちこちで(特に政治方面で)言われている「世代交代」をひしひしと感じて、ちょっと感傷的。
試験が一応終わり、最後の提出物だったFLEの「文章力」を伸ばすための授業に使うテキストの分析と授業案に関するレポートを提出。
Une signe de vie...(いきてます。)
ジャン=クロード・ブリアリが逝ってしまわれた・・・。
Une femme est une femmeを思い出しました。
なんだか、かっこよかった時代の人々がこぞっていなくなってしまうのに、
あちこちで(特に政治方面で)言われている「世代交代」をひしひしと感じて、ちょっと感傷的。
試験が一応終わり、最後の提出物だったFLEの「文章力」を伸ばすための授業に使うテキストの分析と授業案に関するレポートを提出。
 ポジティブ・シンキング。
ポジティブ・シンキング。

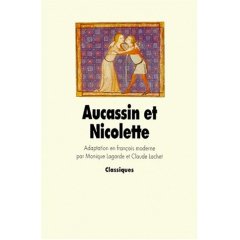 予想通り、一週間「あ」といっている間もなく過ぎる。試験は今週の水曜日からスタートしました。
予想通り、一週間「あ」といっている間もなく過ぎる。試験は今週の水曜日からスタートしました。
 セゴ vs サーコ、on a donc élu SARKO(みんなはサーコを選んだわけだ)。
セゴ vs サーコ、on a donc élu SARKO(みんなはサーコを選んだわけだ)。
 これぞ、フランスの笑い。
それが、
これぞ、フランスの笑い。
それが、



