 明日12月1日(土)スタートのe-corフランス語コミュニケーション教室 クラス・デビュッタント(初心者)へご参加の皆様へのおしらせです。
明日12月1日(土)スタートのe-corフランス語コミュニケーション教室 クラス・デビュッタント(初心者)へご参加の皆様へのおしらせです。
授業は午前10時からです。
用意するものは、筆記用具。
※もしお持ちでしたら日⇔仏辞書。または、仏仏辞書。
教室の場所は こちら ←を参照してください。
車でお越しの方は、NIC駅南の駐車スペースが少ないため、申し訳ありませんが近所の100円パーキングをご利用ください。
皆様にお会いできるのを楽しみにしています!
le haut
 天つ風 雲のかよひ路 吹きとぢよ
をとめの姿 しばしとどめむ
僧正遍昭
天つ風 雲のかよひ路 吹きとぢよ
をとめの姿 しばしとどめむ
僧正遍昭
フランスに居た時に空を眺めることが多くなったと思っていたけれど、
ようく思い出してみれば、小さいときからの癖かもしれない。
雲を眺めながら歩いて、ボチャンとどぶにはまったこともあった。
中学生の頃、部活の帰りはもう夕暮れで、蝙蝠が飛ぶ。
(蝙蝠が飛んでいること自体、衝撃だった。新潟ではよくあることなのだろうか?)
飛んでいる蝙蝠に石を投げると、はっし、とつかむらしいという意味不明のうわさがあって、あほみたいに道端の石を投げまくったこともあった。
(よい子は、危ないのでまねしないでください。)
夕焼けの中にシルエットだけ浮かび上がる蝙蝠。
ちょっと物凄い風景だった。
今、道端に石を見つけるのさえ難しいんじゃないのかなー。
ヨーロッパの空というのは、日本よりも低いような気がする。アイルランドで見た雲は、すぐそばまでやってきて手でつかめそうな気がした。
なんで、こんなに空に惹かれるのか。
古の記憶。
こんな風に、いつかも空を見上げていたのかもしれない。
 新栗の木川の夕暮れ。
新栗の木川の夕暮れ。
Mon amie verte
 6年ぶりのマイカー。記念にと、写真をとったら
まるで空飛ぶ車みたいになった。
6年ぶりのマイカー。記念にと、写真をとったら
まるで空飛ぶ車みたいになった。
以前、父が車を換えるのにたまたま頼んだ販売店の代表が、 偶然にもわたしの小・中学校時代の同級生だった。 と、いっても、わたしは転校生だったし、彼とは一度も一緒のクラスになったことがなかったので、実際面識はあってないようなものだったのですが。 しかしながら、彼、H君は泣く子も黙る「有名人」で、わたしの方はよく存じ上げておりました。笑 そんなびみょーうな関係だったので、再会はお互いなんだか気まずいような、こっぱずかしいような(あまずっぱくはないものの)。。。 探してもらっていた中古車(photo)というのが、たまたま沼垂のあたりで見かけてひとめぼれをした代物だったので、車種も??? Vitzだったんですが。 クラヴィアという限定モノらしくて、道で出くわすことがほとんどないものでした。 夏からずっとオークションで狙ってもらっていたのですが、なにしろマニアックな人気らしくて、走行距離が低いものは結構なお値段。 今回も無理だろうなーと踏んでいたところが、うっかり落とすことができてしまったらしく、彼からの第一報が「買えちゃったんだけど・・・」。 まあ、そんなこんなでやってきたクラヴィアちゃん。 新潟にいなかったので免許取得は遅くて、渡仏の1年前。 それから5年間、フランスでは乗らなかったのでトータル6年のブランク。 一昨年免許更新の時には、ペーパー暦が長いため「次に乗るときはまた若葉マークをつけなさい」と言われて、「なんでじゃ!!」と鼻をふくらませていたものの、 忘れていた。 MT車しか経験がないという、これまたマニアックな己の運転履歴・・・ 試運転では右足でアクセルを踏みながら左足でブレーキを踏んで、 「なんでずっとブレーキランプが点きながら動いてんの・・・?」とH君に つっこまれる。 う、うるさいな、左足が思わず動いちゃうんだもん(MTのなごり)!! よろよろと運転席から出てきたわたしを見て、H君はにやりと笑う。 車の保険屋さんが、やたら事故の詳しいパターンを力説したのは、 きっと彼がわたしのこの怪しさ満点のドライビング・テクニックを報告したからに違いない。 (あれから、一度真夜中の○水フード駐車場にて秘密特訓を行い、無事運転感覚を取り戻しました) ところで、家の駐車スペースは一台分しかとっていなかったため、急遽庭の一部の木を移動してクラヴィアの寝場所を作ったのですが、白樺の木が邪魔になって前のドアが開かず、 現在は後部座席から運転席にもんぐり込んでいる状態です。 うら若(くもな)い乙女が、芋虫のように車に乗り込む姿をご覧になっても ご近所の皆様、どうぞ驚かないでください・・・。 H君はめでたく2児のパパとなり、仕事も順調。 小さかった時の姿がたまに重なって、なんだか不思議に、でもうれしくなる。 暢気なわたしも、がんばらなくっちゃな。 ユーカーズマーケット、車の買い替えを考えている方はぜひどうぞ。
安吾の眼
 お詫びと訂正。11月20日に駅南エリアに配られた新潟日報good morning !!において、e-corの生徒募集が掲載されていましたが、
そちらのお問い合わせ電話番号下四桁が間違っておりました。
正しくは 5751 になります。
大変ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。
***************
お詫びと訂正。11月20日に駅南エリアに配られた新潟日報good morning !!において、e-corの生徒募集が掲載されていましたが、
そちらのお問い合わせ電話番号下四桁が間違っておりました。
正しくは 5751 になります。
大変ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。
***************
フランスから戻ってきて、親友と仲違いをした。 「どうしようもない時」というのはあるもので、 それぞれの人生に対するものの見方、「見つめる」所がまったく食い違ってしまったのが主な理由だった。 たとえて見れば、私は「陽」を見つめ、彼女は「陰」を追い求める、それがお互いに気に食わん、ということになる。 本来ならば、陰陽は正反対ながらも融合するもので、お互いの視線の先がどこを照らそうとそれはそれで、その差異を楽しめて初めて「仲」というのは成立するのかもしれないけれど、様々な要素がからんで、いつの間にかそう楽観できなくなってしまった。 と、思っていた。 小銭を作るのに、たまたま坂口安吾のエッセイ集を買って、実は私自身が大きな「演出ミス」をしていたんじゃないか、と気づくことになった。 18世紀のフランスで、良俗に反すると出版禁止を食らった「危険な関係(Les liaisons dangereuse)」という書簡小説(手紙だけで構成されている小説)がある。 作者はコデルロス・ド・ラクロ。 メルトゥイユ夫人は、愛人が自分の年若い従姉妹の結婚相手になったということがわかって、己の嫉妬心とプライドから、悪友で「たらし」のヴァルモン伯爵に従姉妹を寝取ってしまえとけしかける話。 このヴァルモンとメルトゥイユというコンビは非常に危うい関係で、お互い好き合っているのだけれどそれをストレートに言ってしまうくらいなら死んだほうがマシというねじれ具合。そのねじれは多くの人を巻き込んでしまうトルネードのようで、一度スタートしたらあとは坩堝に向かってまっしぐら。 序文で、出版社側、作者がそれぞれ読者に向けた「注意書き」のようなものを記していて、それが真っ向から食い違っていて面白い。 出版社側は「この作品はあくまでフィクション」だと言い張り、しかし、その次の作者の言い分ではしきりに「これらの手紙は」とか、「書き手それぞれの文法的な・またスタイルの誤り等について作者はできるだけ手をくわえないようにしてある」とか、登場人物すべてが存在することを仄めかす書き方。 安吾はもともと、小説というものは作者の「思想」と「戯作性」がミックスして出来上がっているものだという説を唱えているのだけれど、ラクロの「眼」に着目して、「危険な関係」において、作者は自身の「思想」というものを全く廃した「眼」で見つめ、書いていると言う。作者自身の「思想」が見え隠れしないからこそ、「二百余年の時間的隔たりにも拘わらず、最も近代を思わせる」のだと。 小説家に拘わらず、私たちは「思想」をもち、「戯作性」を発揮して生きているのかもしれない。 生きていると肩書きが色々できて来て、「会社員」「上司」「部下」「取引先の人」「お客さん」は、家に帰れば「バカ息子」だったり「おとうさん」だったり、「妹」、「隣の人」、そして誰かの「愛する人」だったりする。 人の集まる輪の中で、「やり手」だの「天然」だの「いじられキャラ」、「つっこみ」だのという個人の「スタンス」にも役割が与えられる。私たちは、知らず知らずこのレッテルに追いかけられ、格闘をしているのかもしれない。 本人が心から納得して「バカ息子」とか「いじられキャラ」だったら演じ甲斐もあるけれど、現代人の悩みの多くは 「ほんとうの私は、こんなじゃない」 という、「思想」と「戯作」のズレから来ているんじゃないか、と思った。 演出ミスというやつ。 だけど実際には、「周り」の流れに巻き込まれていまさらカミングアウトなんてできる勇気もなかったり、そもそも自分が「がんばって周囲に合わせている」ことに気がつかないでいたり。 がんばることをやめた私は今、安吾の見たラクロの「眼」が欲しいと思う。 安吾がよく言っている「心眼」というものが、欲しいと思う。 娑婆から遠のいて禅の修業で出来上がるものもあるかもしれないが、私はラクロのような、とりあえず全て、「良俗」であろうがなかろうが「肯定的に見る」眼が欲しいと、今思う。 端くれではあるが、私のように外国語を教える立場のものは言葉というものを考え、伝えていく中で、言葉の持つきらびやかな装飾に目を眩まされてその下に息づく魂に気づかないという危うさがある。それを見極められるのは、「心眼」でしかない。 「情痴作家」の言う「人間を直視する」ことを恐れてはいけない。ありのままを見て初めて「良」も「悪」もわかるのだから。
Un art culinaire
 2ヶ月に一回位の割合でフランスの味の試食会をしようかな、と企画中。
某シェフに協力して頂いて、フランスの素朴な味をみんなで楽しみながら発見しよう!というもの。ぜひ楽しみにしていてください。
12月1日(土)スタートのNIC駅南でのグラン・デビュッタン(初心者向け)クラスがe-corの初授業(教室体験)となるので、みんなでパンを食べて、文字通り「copain」(コパン・友達、仲間)を祝ったらどうかな、と考えています。
2ヶ月に一回位の割合でフランスの味の試食会をしようかな、と企画中。
某シェフに協力して頂いて、フランスの素朴な味をみんなで楽しみながら発見しよう!というもの。ぜひ楽しみにしていてください。
12月1日(土)スタートのNIC駅南でのグラン・デビュッタン(初心者向け)クラスがe-corの初授業(教室体験)となるので、みんなでパンを食べて、文字通り「copain」(コパン・友達、仲間)を祝ったらどうかな、と考えています。
コパンの「コ(co)」は、ラテン語のcum「~と一緒に」から来ていて、頭にCOが付いている語は大抵「人々が集まる」という意味合いがあります。
これにパン (pain) がくっついて、ひとつのパンをみんなで分け合って食べる→日本語で言う「同じ釜の飯を食う」仲間なんですね。
最近はフルーツ酵母エキスを作ってパンを焼くのにはまっていますが、酵母を育てる手ごろな瓶がなかなか見つからず。(上のパンは基本中の基本、レーズン酵母で作ったリュスティック。デビュッタントでございます・・・)
料理といえば、先週の土曜日にLa cucina shinobina の「ヨハンナ PAPA GIOVANNA」に行ってきました。
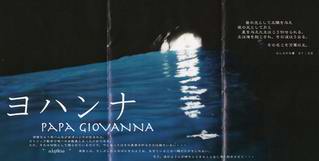
これは横山しのぶさんが定期的に行っている食のルネッサンスを味わわせて下さる大変面白い企画なのですが、今回は旧約聖書の中の「エレミヤの書」からインスピレーションを受けて初期キリスト教時代のお料理をコースにしたものでした。 私はキリスト教徒ではないので(というか無宗教なので)、聖書は大学で文学の一環として学んだ「創世記」とか「出エジプト記」とかモーセの話とか、あとはルネッサンス期のマロによるPsaume(詩篇)なんかしか知らないため、すっかり本棚の奥にしまい込まれていた聖書を出してきて「エレミヤ」を一生懸命探しました。 ジェレミーにたどり着くまでかなりの時間がかかりました。。。(フランス語でエレミヤはJérémieと記されています)。 旧約聖書は、ものすごい量の登場人物に家系図の複雑さが加わり、面白い話が多いのですが試験の時には泣かされましたっけ(自力で家系図をつくったものの、ヤコブの子ジョゼフ辺りで挫折)。 日本人の私に、この「異文化」の元締めとも言えるものが果たして理解できるのだろうか・・・という不安はあってもおかしくありません。 しかし、横山さんが膨大な量の読書と研究の末に見出したものは、 「生きる」ということだった、 と、会の最後でおっしゃった時に「ああ、この大きな『物語』は、そういう風に読めばよかったのか」と初めて聖書の意味がわかったような気がしました。 頂いたお料理はとても知的で多彩で美味しかったのですが、ひとつのパフォーマンスとして料理を「見せる」時に、このテーマは非常に難しいなと思いました。 きっと少人数でひっそり行う方が、伝えたい「真実」は伝えやすくなるのかもしれませんが、それでは宗教色が強くなって、密教会みたいになってしまう危険があります。逆に、今回のように大勢でテーブルを囲むと、散漫になってしまう・・・ なんにせよ、これからもShinobinaがどんな風に表現していくのかとても楽しみです。 それにしても、参考資料の多いこと・・・頭が下がります。
つまりぎみ
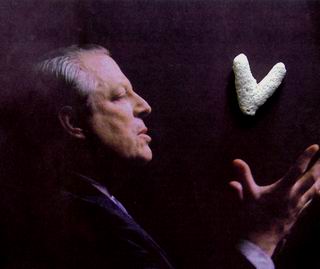 20日の新潟日報のgood morning ! ! (駅南方面)に、NIC新潟で始まるe-corの生徒募集が載ります。
それから、23日に同じく日報のフリーペーパー「assh」にも折込チラシが入る予定です。
20日の新潟日報のgood morning ! ! (駅南方面)に、NIC新潟で始まるe-corの生徒募集が載ります。
それから、23日に同じく日報のフリーペーパー「assh」にも折込チラシが入る予定です。
こういうチラシって、ナントで活動してた時に作ったことはあったけれど、
本格的に折り込んでもらうのは初めて。ドキドキ。
それから、来年四月からになりますが、e-corがカルチャーセンターに登場するかもしれません。
A suivre...(乞うご期待)ってことで、楽しみにしていて下さい。
すでにそちらから来られてこのページをご覧になっている方もいらっしゃるかもしれませんが、「おけいこ広場」にもe-corの紹介をして頂いております。 色々な方の力をお借りして発信できそうです。 ありがとうございます! さて、フランスと言えばスト。ストと言えばフランス。 特に11月は多い月なんですが・・・ SNCFがスト、郵便局もスト、そしてまたもや大学がブロキュス(ブロック)をしています。 Le Mondeでは、前回の大規模なブロキュスですっかり有名人になったUNEF (Union Nationale des Etudiants de France フランス全学連) の代表ブルーノ君と、ヴァレリー・ペクレス 高等教育研究大臣が会見したという記事が載っていましたが、この大臣が言うには、 "Il n'y aura pas, avec la loi, de désengagement de l'Etat (...) pas de sélection à l'entrée à l'université, pas de hausse des frais d'inscription" 「(現在制定を検討中の)新しい法律によって、国が大学経営から手を引くということはないし、[...] 入学試験を新たに行う予定もないし、また入学費用が高騰するようなこともない」 ・・・じゃ、別に改定することないじゃん。 と、思わずつっこんでしまいました。 私も2年前にCPEに反対するデモのお陰でエライ目に合いましたが、 相変わらず学生側も政府側も、どうも空回っているような・・・。 これじゃ学生たちも何のためにストをやっているのかわからなくなります。 母校ナント大学文学部も現在ブロック中。 新学期が始まって(9月スタートです)、ちょうど最初の提出物(小論文)の期限の頃ですから、一部の学生は「助かった!これでいい論文が書ける・・・」と、スト万歳状態なのかもしれません(実話?・・・かも)。 なるべく早く解決するといいですね・・・特に交換留学で来ている人たちのためにも。 「つまる」ってよくない。 便秘が体によくないように、思考停止してしまうとやっぱり不健康だなとしみじみ思います。
ゆらぎ
 フランス語を教えるのにHPを新しく作って、
第一弾の話題がこれか、と言われそうなのですが、
ま、ま、ちょっとお許しを。
フランス語を教えるのにHPを新しく作って、
第一弾の話題がこれか、と言われそうなのですが、
ま、ま、ちょっとお許しを。
わたしが1年前から教えていただいている太極拳の師匠「○さん」は探究心の権化のような方だと常々思っている。 昨日、皆さんの前でストレッチについて色々と「悩んでいる」と打ち明けていらっしゃったけれど、確かに、日々練られているなという感じがする。 わたし個人の感想としては、「それが、いい。」 教えるということに関しても、その人の"façon"(やり方)というものがあって、それが合うかどうかというのは個人の感覚による。 人によっては、「教え方が一定しないのはどうよ」と眉をひそめる。 わたしも、以前は「かくあるべし」と言ってくれたほうが、安心できると思っていた。 けれど、「不動」というのは生物の本来の姿を表していないのじゃないかと、最近は感じる。 だから、教える人が学ぶ人と一緒にゆらいでいる、そういうのが心地いい。 ゆらいでいるのがわかる先生と一緒に変化していきたいと思う。 ただ、揺らいでいる部分、「あそび」の部分というのはあくまで枝先であって、 根っこがふらふらしているのとは違う。 太極拳を伝えていく、伝えた人が他に伝えやすいように作り上げていくために、揺らぎ、考え、試している、それを○さんは 「ひとつの作品を創っているようなもので」 とおっしゃる。 確かに、芸術作品の創造に立ち会っているようなもんだなーと感心していたら、 いきなり 「フランス語だってそうでしょ?」と言われて、 一瞬古代ギリシャ・ラテンからの歴史が渦を巻いてわたしの中に押し寄せ、なんと言っていいやらわからず、 「はあ、いや、はい、そうです」 と、ものすごいあいまいな返事をしてしまった。 ゆらぎはゆらぎでも、動揺するようではまだまだです。 何はともあれ、 わたしも、どっしりしながらゆらゆらとフランス語と付き合っていこう。 末永く、どうぞよろしく。
RENOVER
ご無沙汰しております。はるか昔に予告しましたが、 一新のおしらせです。 新潟で活動を始めるのにあたってHPを作りました。 http://ec0r.com (eとrの間は数字のゼロです) BLOGはHPの日記ページに移ります。 。。。と、思ったのですが、どうやらJUGEMの方が見やすいので、 こちらで引き続きフランス語とわたしの日々を記して行くことにしました。 こうなるんじゃないかと思ってた。 お騒がせをいたしました。 これからもどうぞよろしくお願いします。








