各分野の目的を知ること
DELF/DALFの要項を見ると、試験の内容が分かれています。
口頭(Oral)では
Compréhension de l'oral(CO) Production de l'oral (PO)
筆記では
Compréhension de l'écrit (CE) Expression (Production) de l'écrit (PE)
これは、ただただ分かれているわけではなく、それぞれの能力をより明確に評価するための分野分けになっているのです。
まず、チャレンジする方々に知っておいてもらいたいのは
それぞれのカテゴリーの「目的」が何なのかということ。
たとえば「Compréhension」では、「理解力」があるかどうかを評価します。 なので、たとえば1点の問題で、自由表記、自由回答の場合(つまり、マークシートで選ぶものでない)あなたの答えの文法が間違っていようと、表現が不適切であろうと、問われた内容に当てはまる答えを出せば、 1点貰えるのです。 ちょっと肩の荷が下りませんか? 要は、あなたが問題のcontexte(内容)を理解し、問いを理解している、ということを証明できれば、高度なことを書いたり述べたりする必要はありませんし、文法とか表現力について、「Compréhension」の分野ではそれほど気にしている時間がないのです。
会話でリスニング訓練は効率が悪い?
Oralはリスニング力と口頭での表現力を問われます。 フランス語を話すお友達と会話で鍛えるというのは、「表現」の分野ではとても有効な方法です。まず、「外国語をしゃべる」という状況にすんなり入っていけるからです。 けれど、DELF・DALFのリスニング力を鍛えるには、実は、イマイチがつんと来る手法ではないのです・・・。
試験でよく使われるのは、ミニダイアローグであったり、レベルが上がるとラジオの録音だったりします。特にDALFになるとラジオのルポタージュが多いです。
Parenthèse : 私がフランス人と会話していてよく思うことなのですが、 初対面の人だと、どんなに気をつけて話しても、お互いに話がきちんと通じる可能性は、友達や顔見知りと話す時より30%ほど落ちてしまいます。 これは、ある意味仕方のないことで、マインドの影響が多いからだと思います。慣れていないフランス人は、私が発言したり話しかけたりするとき、非常に緊張してなんとか私のアクセントを聞き取ろうとするため、妙なtensionが一気に上がります。私の言うことがわからなかったら私を傷つけてしまう、という心配りからなのでしょうが、実は裏を返すと
「こいつの言うことは注意して聞かないとわからない、なぜなら外人だから」
と、思い込んでいることからくるのです。
もちろん、こちら側も「私の表現変じゃないかしら」「意味通じるかしら」と不安から力んで発音したりして、お互いに相互理解を阻んでいるというおかしなことになります。
ヨガをやっていて、身体の固まっている状態を伸ばしていくとき、痛いのを防ごうとものすごい力を入れているのに気がつきます。呼吸を繰り返していくうちに、それがふっと緩むときがあり、まるで「かぱ」と身体のふたが開いたような感覚を持ちます。 リスニング力も、身体に力が入っていると、全身のふたがびしっと閉まってしまうのです。 Parenthèse 閉めます(笑)。
それでも、生の人間に向かい合っているときには意思疎通が、見えたり聞こえない部分でできます。いわゆるテレパシーのようなものですが、思いというのは通じる力があるからです。 けれど、試験の時目の前にあるのは無愛想なスピーカー。そしてこちらは非常に緊張した状態。これでは普段わかることもブロックかかりまくりなのです。 ラジオやテレビは時間が限られているのもあり、独特の表現もあるため、ものすごく早く感じてしまいます。いくら普段友達と会話するのに慣れていても、このスピードについていくには、とにかく慣れるしかないのです。













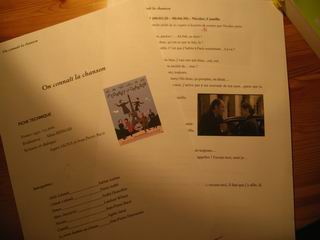 KiKiさんのところで、フラ語学習者に非常に恐れられていることがわかった「接続法」
または、「バカ殿法」。「アィーン法」。「シムケン法」
などとわたしは呼んでいます。(なぜなら、活用が「アィーン」と横にずれる音になることが多いので:
KiKiさんのところで、フラ語学習者に非常に恐れられていることがわかった「接続法」
または、「バカ殿法」。「アィーン法」。「シムケン法」
などとわたしは呼んでいます。(なぜなら、活用が「アィーン」と横にずれる音になることが多いので:




