もーえーつーきーたー・・・締め切りを破って早2週間。新学期が始まった一週間のうち3日完徹。(友達には「何をそんなに疲れてるわけ?」と不思議がられた) ついにレポート完成。「Influence de l'alphabet sur la langue et sur la culture japonaises(日本の言語と文化におけるアルファベットの影響)」全29ページなり。 3日間くらいまともにご飯を食べなかったら体重2キロ減。 慣れていたつもりのWordにこんなに手こずらされるとは、不覚です。何度 「このtétu!!(テテュ、頑固者)」とパソコンに向かって罵倒したか分からない。 確かにレイアウトとかやったことなかったし、こんなに図表をたくさん入れるものを作ったことはなかったしなぁ。日本語でもこんなにたくさんの枚数書いたことなかったし。 しかも、フラ語のスペルチェックに1日、文章構成のチェックに2日はかかっているし。これだけやっても、きっとおばかなミスがあるんだろうなー・・・ハァ。 我がとろいとろけた脳みそを「与太郎」と名づけました。(与太郎は落語の世界ではある意味主役と言ってもいい、気は良いけれど非常識が服を着て歩いているようなのんびり天然キャラ。) 新学期が始まって愕然としたのは、今学期から「古フランス語」の授業があるということ。もうすでにラテン語と英語でいっぱいいっぱいなんすけど・・・。それ以前に、フラ語さえ思うように行かない、いや、日本語さえわけが分からないのに。 「頭よくなりたい。今すぐ!」と日本の友達に訴えたら、 「青魚を食べろ」 と、返事が来ました。 鯖買いにいくか、サヴァ!
Xの悲劇
X-barre
好きなもののひとつが、この科目。 このシェーマを見ただけだと「うげーー!!」と言われそうなのですが、意外にパズルのようではまるのです。フラ語脳がしゃっきりする。フラ語が正しく使えてないところとか、普段あいまいにしたまま誤魔化しながら使っているところがはっきりする。 これはナント大文学部の2年で習う言語学の授業の1つ、「Morpho-syntaxe」の中の「Théorie X-barre」というやつ。エックスバー理論と言うんだろうか。日本の大学を出てないので日本の仏文専攻の人たちがこういうことをやるのかどうかさえもわからないんですが。 この言語学系の授業は必須で、一年の一学期で大まかなフランス語文法のおさらいをし、同時に言語学の一番ベースになるフラ語の歴史(派生とか人間の脳の進化についてとか)と言語の分類などを習い、2学期には主にラテン語からフラ語への発音の進化を学習します。 2年目に「形態論」というやつを始めます。 文法に出てくる専門用語って、フラ語だとすごいわかりやすいのに日本語になるとやたら圧迫感を感じる言葉になるのが不思議です。 フラ語だと「Morphologie(モーフォロジー、英語だとMorphology)」って、響きもなんとなく和めるんですが「形態論」とか言われると圧迫を通り越して軽い恐怖を感じるのは私だけ? 何をするのかというと、最終的にフラ語の文章を上の図のように分解して、何がどこにどうつながっているのか、というのを単語単位で説明するもの。法則が色々あるので、それを知っていれば知識のない言語でも上のようなシェーマを組み立てることが出来る。昨日の試験ではナイジェリア語が出題されました。 授業ではフラ語とまったく逆の図式ができる日本語も時々例に出されていたけれど、日本語の文章はフラ語よりややこしい式になる気がします。 この言語学を始めて、自分の日本語に前より少し敏感になった。「テニヲハがおかしい」かもしれないなんてこと、以前は考えもしなかったけれど、実際に文法上正しくない日本語を書いていることが多い。 文章を書くということは、言語を使った立体画像を描くようなものなんじゃないかと、バイリンガルになってから思うようになった。 ボタンを押すとブィン、と3D画像が現れてそれがしゃべったり動いたりする。昔から未来が舞台のスパイ映画とかロボットアニメとかでおなじみのシーン。あんな感じ。 言葉一つ一つが立体画像を作り出すボタンのようなもので、読んでいくにつれてボタンが押されて画像が浮かび上がる。書き手の内部が読み手の内部に再現される。 イメージやアイデアは、クンデラが言っているようにむしろリキッド状に近い。もやもやとしていて、まだ形態をもっていない。それを言葉で表すというのは一種の化学変化を起こすみたいなものだ。 「もやもや」に一番相応しい言葉を吟味する。文章のリズムや選んだ言葉が「もやもや」に色や形、匂い、感触などを与えて、1つの明確なイメージになる。 絵画だから、人それぞれ使う色もテクニックも違うし、読み取るほうが書き手と同じ手法で描くとは限らない。だからおもしろい。 今まで、私はこの「絵画」をものすごくぞんざいに扱っていた。自分の内面に浮かぶものを、根気よく丁寧に描き出すことができずにいた。 作家じゃなくても、この言葉の絵画をきちんとできる人はたくさんいる。 そういう人を見ていると、「考える」ということを億劫がらないひとなんだなと思う。 めんどくさいなあと思うけれど、きちんと考えないまま発信すると余計な誤解を生んだりしてしまう。 発信された言葉を受け取った時、人は「言葉を理解した」と思う。けれど、同時に、言葉にまとわり付く「匂い」みたいなものも無意識でキャッチしていて、実は言葉の記号そのものよりも「匂い」のほうが一番心の深いところに響いたりする。 この「匂い」って、その人の人間性や深層心理なんじゃないかな、と思う。 だから、言葉でほめられても、ほめた人がものすごく嫉妬していたりしたら受け取った側はほめ言葉に傷つけられるということがあるし、ただ「はぁ」という相槌で「うれしい」とか「悲しい」という感情の悲鳴がびりびりと伝わったりもする。 「私の言っていることが世間的に正しい」という人がくれた倫理的なアドヴァイスより、「君よ、幸せであれ!」と願っているひとがにこっと笑ってくれた、それだけに励まされたりする。 考えたか考えてないか、っていうのは何かを話すときには隠してもばれちゃうなあと思った。 特に、人に何かを頼むとき。友達同士でも、「これ頼むわ、でも見返りはないからね」とか言われたら頼まれた方は「あたしゃ、あんたのドラえもんかよ!」と腹が立つかもしれない。 聞く前に、自分で出来る限りのことをしたかどうか。相手の状況、忙しさとか、頼まれた時の負担とか、考えることはたくさんある。 普段からどれだけそういうことに考えを馳せているかというのが、実際に会ったり話したりした時に、コミュニケーションの実力として発揮される。 上手に出来なくても、かっこ悪くても、考え方が足りなくても、 やろうとした、そういう心意気に、愛情とか友情とかを感じるんだと思う。 長くなりましたが、そんなわけで、特にうそつきで人を困らせたりはしていなかったけれど、元旦に、目標は「正直」と思ったわけです。 普段の会話でいちいち上に書いたようなことを考えていたら疲れてしまうし、受け取ったほうも重い。けれど「正直でいる」というのは、自分をも相手をも敬うことだし、歯磨きと同じように毎日やることなんだろうな、と思っています。 上のXバー、昨日の試験の問題だったんですが、今やり直してみて間違いに気づいた・・・ショック!(出題の文章はLe juge au fils duquel Berthe confiait très souvent ses grands chagrins a finalement quitté Nantes la semaine dernière. 「ベルトがよく自身の深い嘆きを聞いてもらっていた裁判官の息子は、先週ついにナントを発った。」ややこしー。)
根本思想
ネットの心理テストサイトの結果。「恋人に謝るときの謝罪の言葉・行動」わたしの答えは、 芸をする。 絶対許してもらえそうにない。 ていうか、「今の芸が面白かったから許す」という懐の広いお方がいらっしゃったら結婚して欲しいです。 日本じゃ結構有名なものかもしれない心理テスト。去年帰国したときに教えてもらってみんなでやたら盛り上がった。 深く考えずぱっと思いつくままに、理想の相手の条件を5つ挙げて1番から5番まで番号を付けてください。 たとえば、①やさしい人②お金持ちの人③きれい好きな人、などなど。 答えは下。
答え 2番目に挙げた答えが、あなたの深層に潜む理想の相手の条件だそうです。 まりの2番目は「面白い人」でした。さて、当たっているのか・・・ ちなみに、教えてくれた友達の2番目は「次男」だった。うーん。
Cauchemar
中村吉右衛門の講演会に行った。吉っつあんは、午前の部と午後の部の合間の休憩時間に、しょぼい会議用デスクを組み立て端っこでガレットを売り始める。 手のひらサイズのホットケーキみたいなまがい物で、一枚2000円。高! しかも、メニューに書かれたガレットの中身の1つが「卵尽くし」。曰く、「鶏卵・鶉の卵・ダチョウの卵」 そ、そのまんまだ・・・。添えられた写真には大中小揃い踏みの目玉焼きさんたちがお目見えする謎のガレットが。 一緒に来た友達が、殿様が乗る籠についてのレポートを書いたと言ったら、ガレットを焼きながら吉っつぁまは大層喜び、ぜひ午後の部で発表をしてくれと友達に言う。 午後の部が始まって、教壇に立ったのは 三遊亭円楽だった。 という、悪夢を見た。 誰か、この、なんかもうどうにもならない夢の解釈をして下さい。 中村吉右衛門さんは、わたしが一番好きな歌舞伎役者さんで、鬼平犯科帳と言えばこの方以外には考えられない、そして、フランスのわが家に張られた「石川五右衛門」のポスターは、その昔、手に入れるために駅に張ってあるものをはがして逃げようかと、犯罪を覚悟するほどだった、そんな、日夜拝んでいるような方なのですが。(ポスターは歌舞伎座で正規に購入いたしました。) 円楽師匠もね、復活なさってようござんしたと、遠くから回復を喜んでいたんですけどね・・・。でも、わが愛・吉つぁんが、中身だけそのままで(といっても中身を知っているわけじゃないんだけど)、いきなり円楽の姿で出てこられたら、誰だって「ぶっしゅべー」(bouche bée、口をぽっかりあけた様子、つまり驚愕。)になります。 わたしの夢の筋が八方破れにドラマチックなのは元々だったけれど、この悪夢?はリストアップして置くべきだと思いました。
危険な関係
 危険な関係
だらだら映画日記。
1959年に公開されたロジェ・ヴァディムのこの映画の原作は、同名のコルデロス・ド・ラクロの小説。登場人物や関係はそのまま、時代を18世紀から20世紀のフランスに移したもの。
ジェラール・フィリップといえば、わたしにとっては「銀幕の貴公子」ではなく、「カリギュラ」。
「カリギュラ」はカミュの戯曲で、腐敗した宮廷に反発して暴君となり、権力に溺れる貴族たちを虐殺していくローマ皇帝カイウス・ジュリアス・カエサル・ゲルマニウスを描く。カリギュラは若くゆらゆらと夢を見ているようで、天才的な哲学的頭脳をもてあまし、不思議な透明感を持つカミュ特有の主人公とも言える。
この「危険な関係」、「Les Liaisons dangereuses リエゾン・ダンジュローズ」はジェラール・フィリップが出演した最後から2番目の映画。カミュが自動車事故で亡くなるのを知っていたかのように、37歳でこの世を去ってしまった。癌だった。
ジェラール・フィリップがお気に入りの俳優ではないし、特別上手いと感じたことがあんまりないのだけれど、この作品の彼は好きだ。本当に彼のいい部分を上手に引き出していて、ぴたりとはまっている。彼の童顔に、世慣れたおやじっぷりがそこはかとなくかもし出されてきて、いい味になってきていた。もっと色んな作品を見たかったなと思わせる。
原作は当時(1782)のフランスではかなりスキャンダラスで、一時は出版禁止を食らった。17世紀後半から流行し始めた「書簡小説」というもので、手紙だけで構成されているもの。社交界では「たらし」で有名なヴァルモン子爵と、美貌と頭の良さで常に男を虜にするメルトゥイユ伯爵夫人の「危険な関係」に巻き込まれる人々のお話。
マダム・メルトゥイユは自分の元恋人が若いセシルと結婚することを知って、仕返しに「共謀者」のヴァルモンにセシルの処女を奪ってしまえという指令を出す。一方ヴァルモンは人妻のトゥルヴェル夫人に本気になってしまい、それが元で嫉妬と愛情がもつれたヴァルモンとメルトゥイユの関係は次第に狂い始め、それぞれの破滅に向かっていく。
映画ではこのヴァルモン・メルトゥイユを夫婦にしているので、原作を知っていれば簡単にこの二人の関係が理解できる。「本気にならない」という暗黙の了解の元にお互いが愛人を作っては捨て、一部始終を報告しあうという、見かけは美しいが性格の悪いカップルをジェラール・フィリップとジャンヌ・モローが演じる。
惜しいのは、せっかくはまり役のジャンヌ・モローなのに、原作で描かれるメルトゥイユの深層心理や、彼女の、プライドからヴァルモンに対する素直になれない愛情や、観察眼の深さ、彼女自身の変化が十分に描かれていない。ジャンヌ・モローはへたくそな女優ではないのだから、これは脚本に問題があるのかもしれない。
1回目に見たときからなんか物足りないなーと思っていて、昨日久しぶりに見てわかったのは、箱入りお嬢ちゃんのセシルがバカっぽいだけで可愛くないのがまずかったのでは、ということ。ジャン=ルイ・トランティニォンの役立たずな青年っぷりがいい感じなのだけれど、セシルがなんだか可愛くないので、彼が彼女を横取りされて逆上するところがなんとなく頷けない。しかも、その逆上がヴァルモンを死に追い遣ることになるのだから、セシルはぶりっ子で可愛い女優にして欲しかった・・・。といっても、誰がいいか思い浮かばないんだけれど。
原作は気合の入った濃厚さで、いわゆる「エスプリ」というものがたっぷり盛り込まれ、男女の心理的な戦いが手紙の中で交わされているのだけれど、その辺が50年代のフランスに置き換えられたらなんとなくジャズとおしゃれな雰囲気でごまかされたような気がしてしてしまう。
ロジェ・バディムは他にはBB(ブリジット・バルドー)主演の「月夜の宝石」を見たことがあるけれど、部分的に印象に残るカットがあるんだけれど映画全体がなんだかぼやけてよく思い出せないといった感じ。
「危険な関係」では、メルトゥイユ役(映画では「ジュリエット」という名前になっている)のジャンヌ・モローが、旦那のヴァルモン(ジェラール・フィリップ)がうっかり本気になってしまった愛人のトゥルヴィル夫人(映画では「マリアンヌ」)との関係に嫉妬し、終止符を打たせるために、彼の名で別れの電報を送る。ヴァルモンは「たらし」のプライドから、それを止める事ができない。その電報が届く4時のシーンがいい。
ロッキング・チェアーの背に固定されたカメラがヴァルモンの背中を映し出す。柱時計の音。チンチンと4時が鳴る。ヴァルモンはくわえタバコで立ち上がり、腕時計と柱時計を見比べる。「Exécuté(エグゼキュテ)」というと再びロッキング・チェアーに座る。
Exécuté(エグゼキュテ)は「実行された」という意味で、電報が届けられたことを示すと同時に、「処刑執行」の意味も持つ。ヴァルモンを信じて自分の夫とも別れたトゥルヴィルに対する「処刑」とも取れるし、心から夢中になったヴァルモン自身の愛が「処刑」されたとも取れる。原作にはないシーンだけれど上手い。
日本でもDVDが出ているみたいです。
今ジェラール・フィリップで見たいのは「Le Joueur(勝負師)」。ドストエフスキーの原作をフラ語で読んだのだけれど、すっかり夢中になった。しかし、ジェラール・フィリップのこの映画はフランスではすっかりマイナーで見当たらず。日本で買うと高い・・・。うー。
危険な関係
だらだら映画日記。
1959年に公開されたロジェ・ヴァディムのこの映画の原作は、同名のコルデロス・ド・ラクロの小説。登場人物や関係はそのまま、時代を18世紀から20世紀のフランスに移したもの。
ジェラール・フィリップといえば、わたしにとっては「銀幕の貴公子」ではなく、「カリギュラ」。
「カリギュラ」はカミュの戯曲で、腐敗した宮廷に反発して暴君となり、権力に溺れる貴族たちを虐殺していくローマ皇帝カイウス・ジュリアス・カエサル・ゲルマニウスを描く。カリギュラは若くゆらゆらと夢を見ているようで、天才的な哲学的頭脳をもてあまし、不思議な透明感を持つカミュ特有の主人公とも言える。
この「危険な関係」、「Les Liaisons dangereuses リエゾン・ダンジュローズ」はジェラール・フィリップが出演した最後から2番目の映画。カミュが自動車事故で亡くなるのを知っていたかのように、37歳でこの世を去ってしまった。癌だった。
ジェラール・フィリップがお気に入りの俳優ではないし、特別上手いと感じたことがあんまりないのだけれど、この作品の彼は好きだ。本当に彼のいい部分を上手に引き出していて、ぴたりとはまっている。彼の童顔に、世慣れたおやじっぷりがそこはかとなくかもし出されてきて、いい味になってきていた。もっと色んな作品を見たかったなと思わせる。
原作は当時(1782)のフランスではかなりスキャンダラスで、一時は出版禁止を食らった。17世紀後半から流行し始めた「書簡小説」というもので、手紙だけで構成されているもの。社交界では「たらし」で有名なヴァルモン子爵と、美貌と頭の良さで常に男を虜にするメルトゥイユ伯爵夫人の「危険な関係」に巻き込まれる人々のお話。
マダム・メルトゥイユは自分の元恋人が若いセシルと結婚することを知って、仕返しに「共謀者」のヴァルモンにセシルの処女を奪ってしまえという指令を出す。一方ヴァルモンは人妻のトゥルヴェル夫人に本気になってしまい、それが元で嫉妬と愛情がもつれたヴァルモンとメルトゥイユの関係は次第に狂い始め、それぞれの破滅に向かっていく。
映画ではこのヴァルモン・メルトゥイユを夫婦にしているので、原作を知っていれば簡単にこの二人の関係が理解できる。「本気にならない」という暗黙の了解の元にお互いが愛人を作っては捨て、一部始終を報告しあうという、見かけは美しいが性格の悪いカップルをジェラール・フィリップとジャンヌ・モローが演じる。
惜しいのは、せっかくはまり役のジャンヌ・モローなのに、原作で描かれるメルトゥイユの深層心理や、彼女の、プライドからヴァルモンに対する素直になれない愛情や、観察眼の深さ、彼女自身の変化が十分に描かれていない。ジャンヌ・モローはへたくそな女優ではないのだから、これは脚本に問題があるのかもしれない。
1回目に見たときからなんか物足りないなーと思っていて、昨日久しぶりに見てわかったのは、箱入りお嬢ちゃんのセシルがバカっぽいだけで可愛くないのがまずかったのでは、ということ。ジャン=ルイ・トランティニォンの役立たずな青年っぷりがいい感じなのだけれど、セシルがなんだか可愛くないので、彼が彼女を横取りされて逆上するところがなんとなく頷けない。しかも、その逆上がヴァルモンを死に追い遣ることになるのだから、セシルはぶりっ子で可愛い女優にして欲しかった・・・。といっても、誰がいいか思い浮かばないんだけれど。
原作は気合の入った濃厚さで、いわゆる「エスプリ」というものがたっぷり盛り込まれ、男女の心理的な戦いが手紙の中で交わされているのだけれど、その辺が50年代のフランスに置き換えられたらなんとなくジャズとおしゃれな雰囲気でごまかされたような気がしてしてしまう。
ロジェ・バディムは他にはBB(ブリジット・バルドー)主演の「月夜の宝石」を見たことがあるけれど、部分的に印象に残るカットがあるんだけれど映画全体がなんだかぼやけてよく思い出せないといった感じ。
「危険な関係」では、メルトゥイユ役(映画では「ジュリエット」という名前になっている)のジャンヌ・モローが、旦那のヴァルモン(ジェラール・フィリップ)がうっかり本気になってしまった愛人のトゥルヴィル夫人(映画では「マリアンヌ」)との関係に嫉妬し、終止符を打たせるために、彼の名で別れの電報を送る。ヴァルモンは「たらし」のプライドから、それを止める事ができない。その電報が届く4時のシーンがいい。
ロッキング・チェアーの背に固定されたカメラがヴァルモンの背中を映し出す。柱時計の音。チンチンと4時が鳴る。ヴァルモンはくわえタバコで立ち上がり、腕時計と柱時計を見比べる。「Exécuté(エグゼキュテ)」というと再びロッキング・チェアーに座る。
Exécuté(エグゼキュテ)は「実行された」という意味で、電報が届けられたことを示すと同時に、「処刑執行」の意味も持つ。ヴァルモンを信じて自分の夫とも別れたトゥルヴィルに対する「処刑」とも取れるし、心から夢中になったヴァルモン自身の愛が「処刑」されたとも取れる。原作にはないシーンだけれど上手い。
日本でもDVDが出ているみたいです。
今ジェラール・フィリップで見たいのは「Le Joueur(勝負師)」。ドストエフスキーの原作をフラ語で読んだのだけれど、すっかり夢中になった。しかし、ジェラール・フィリップのこの映画はフランスではすっかりマイナーで見当たらず。日本で買うと高い・・・。うー。
フラ語ハツワライプロジェクト始動
 あけましておめでとうございます。
みなさまどうぞ今年もよろしくお願いいたします。
2006年の目標
一、早起き
一、正直
一、よく働く
ええもう、動き出したくてうずうずしています。試験勉強もう飽きました。
全国の受験生の皆さんの苦しみを分かち合えたような気にさえなってきました。
(飽きたので古典作家諸先生のいい男比べとかやったりしていました。個人的にはモリエールとヴォルテールはいい感じです。ラ・フォンテーヌはあきまへん。)
あけましておめでとうございます。
みなさまどうぞ今年もよろしくお願いいたします。
2006年の目標
一、早起き
一、正直
一、よく働く
ええもう、動き出したくてうずうずしています。試験勉強もう飽きました。
全国の受験生の皆さんの苦しみを分かち合えたような気にさえなってきました。
(飽きたので古典作家諸先生のいい男比べとかやったりしていました。個人的にはモリエールとヴォルテールはいい感じです。ラ・フォンテーヌはあきまへん。)
 初笑いプロジェクト
「あり得ないものカタログショー」
フランス的「バカドリル」? CATALOGUE D'OBJETS INTROUVABLES からバカオブジェをピックアップしてまいります。
オブジェNo.1 トータル・ロッキングチェアー
初笑いプロジェクト
「あり得ないものカタログショー」
フランス的「バカドリル」? CATALOGUE D'OBJETS INTROUVABLES からバカオブジェをピックアップしてまいります。
オブジェNo.1 トータル・ロッキングチェアー
 Rocking-chair total. Perfectionnement du rocking-chair classique, celui-ci permet de faire un tour COMPLET! Il est recommandé lors de son utilisation, de s'attacher avec la ceinture de sûreté prévue à cet effet.
伝統的スタイルのロッキングチェアーの動作を極めたこちらの商品は、コンプリートな揺れを提供いたします!尚、ご使用の際は付属の揺れ専用ベルトに身体を固定していただくようお願いいたします。
※Tous nos articles sont garantis absolument inutilisables.
ご紹介する全ての商品は100%使えないことを保障いたします。
今年はもっと気合を入れてフラ語を笑いたいと思っています。
まり
Rocking-chair total. Perfectionnement du rocking-chair classique, celui-ci permet de faire un tour COMPLET! Il est recommandé lors de son utilisation, de s'attacher avec la ceinture de sûreté prévue à cet effet.
伝統的スタイルのロッキングチェアーの動作を極めたこちらの商品は、コンプリートな揺れを提供いたします!尚、ご使用の際は付属の揺れ専用ベルトに身体を固定していただくようお願いいたします。
※Tous nos articles sont garantis absolument inutilisables.
ご紹介する全ての商品は100%使えないことを保障いたします。
今年はもっと気合を入れてフラ語を笑いたいと思っています。
まり
続 はじめての落語 志の輔ひとり会
日本のすごいものを、フランスに居ながら体験してしまった。しかも、LIVEで。そこがすごい。 ほぼ日刊イトイ新聞&第2日本テレビPresents 続 はじめての落語 志の輔ひとり会 インターネット中継で、高座の合間に特設こたつステージでの立川志の輔と糸井重里の落語対談。 志の輔師匠はフランス時間で朝7時位から午後17時位まで途中ほんの1時間ばかりの休憩を挟んでしゃべる。 落語をやり、こたつで語り、舞台の袖に戻ってきて今度はインターネットを見ている人に向かって語る。 舞台から降りてきた志の輔師匠を見て、はじめて落語家ってかっこいいと思った。 「すごい」とか「うまい」とか「いい」とか思ったことはあったけど、 「かっこいい」はなかったなあ! しかも、インターネットでは高座を見ることが出来ないのに、戻ってきた面々の顔や師匠本人の顔を見るだけで、高座がすごかったんだなとわかるというのは、すごい。 高座に上がる前は食べないというので、どんどん消耗しているのが画面を通しても明らかだったんだけど、落語家が高座から降りてきた姿というのはあまり見る機会がないから余計に新鮮でした。 落語というものをちゃんと知ろうと思うようになってから、ようやく半年といったところだけれど、知れば知るほど不思議な世界だと思う。 こたつで二人が話していたことというのは、とてもシンプルで、知っていると人生が豊かになることだった。 志ん生の高座の録音で、長屋のおかみさんが「なんでダンナと結婚したのか」と聞かれて 「ん、だって寒いから」 というのだが、そう言えるっていうのは夫婦愛の究極だという話があった。 志の輔さんは、落語を通して人は、言葉そのものには見えてこないけれど伝わるものが確実にあるということを知る、と話していた。 それをどれだけキャッチできるかは、噺家の発信の仕方もあるけれど、お客さんの「こころのフィルター」がどれだけ繊細に出来ているかということ次第にもなる。 人は、笑う時も泣く時も怒る時も嬉しい時も苦しい時も、揺れる。 「感動」は、感じて「動く」。 この揺れを、わたしは実現したいんだと思った。 揺れた時、その振動の中から深いところに沈んでいる「自分」というものが、必ず現れてくる。その揺れは空間を伝わって人から人へ伝っていく。 そうして、ひとりひとりが揺れては自分を感じることになる。 わたしは、この先何に関わるにしても、誰と居るにしても、何を創るにしても、揺れていたい。ゆらゆら、ゆらゆら、心地よく笑っていよう。
本日のお言葉 Proverbe africain
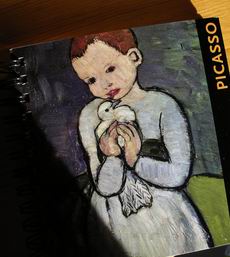 Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens.
一体どこに向かったらいいのかわからなくなった時は、
今まで来た道を振り返ってごらん。
アフリカの諺
ここに抜粋する言葉(シタシォン)たちは、主に
evene.fr 内のcitations du mondeより抜粋しています。
シタ邦訳:まり
※わたし自身が原語(フラ語・英語・ラテン語)から感じ取ったものをわたし自身の言葉で訳してありますので、一般に公開されている邦訳と解釈が違う可能性があります。
そのほかのCitation
Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens.
一体どこに向かったらいいのかわからなくなった時は、
今まで来た道を振り返ってごらん。
アフリカの諺
ここに抜粋する言葉(シタシォン)たちは、主に
evene.fr 内のcitations du mondeより抜粋しています。
シタ邦訳:まり
※わたし自身が原語(フラ語・英語・ラテン語)から感じ取ったものをわたし自身の言葉で訳してありますので、一般に公開されている邦訳と解釈が違う可能性があります。
そのほかのCitation
クリスマスプレゼント
 12月は課題やスピーチの準備で忙しかったので、2週間ほどお休みをしていたバイト。久しぶりに復帰したのだけれど、これが今年の働き納めになった。
バベさんの奥さんは手先を動かすことが好きな人で、暇さえあれば洋服を作っている。この前はエルメスに行くというから、さすがマダムは行く店が違いますな、と思ったら、「スカーフを作ろうと思うんだけど、去年ウィンドウで見かけたおもしろい形のエルメスのやつを参考にするためのリサーチ」だったり。
わたしが彼らの家に週一回のお掃除人として働きに行くようになるちょっと前に、ポーセリンの絵付け講座を始めたらしく、たまに下絵や焼きを入れる前の乾かしているお皿なんかがサロンに置いてあったりした。
初期の作品は小さなものが多かったけれど、今は、貝型の大きなお皿に、うねる波をすれすれに飛ぶかもめとか、大きな丸皿に幻想的なお城とか、どんどん大作になってきている。
中でもわたしが気に入って、掃除機をかけたり戸棚を磨いたりしている間にいつも眺めていたのがこの小さなお皿。
筆先はまだ慣れておらず心もとない感じだけれど、素朴。火の鳥の赤ちゃんみたいな燃えるような羽と、首の青さがなんとも気持ちがいい。
奥さんはわたしがこのお皿を特別に気に入っているのを知っていたらしく、今日わたしを食堂に呼ぶと、お皿を包んでくれた。
「マリはいっつもこのお皿を眺めていたの知っているのよ」と、にやりとすると、「だから、あげます。ノエルのプレゼント。」
実は、バイトを止める時には思い出に譲ってもらえないかどうか聞こうと考えていた位、このお皿のことを思いつめて(!)いたので、ちょっとびっくりした。
プレゼントに一番必要な要素って、「思いがけなさ」なんじゃないかな、とふと思いました。「くるぞくるぞ」と思っているときに、期待していたものと違うものが来たりすると、ありがたいやらありがたくないやら、と途方に
暮れたりするけれど、全く予期していないときに何かを貰った時、それがたとえポストカード一枚でも嬉しくなったりするんだろうな。。。
そう考えると、クリスマスにプレゼントとか、バレンタインにチョコとかって、わかりきっているだけに難しい。
バベさんの奥さんは夏に手術をしたりして、体調があまり芳しくない。
どうぞ元気でいてください。
12月は課題やスピーチの準備で忙しかったので、2週間ほどお休みをしていたバイト。久しぶりに復帰したのだけれど、これが今年の働き納めになった。
バベさんの奥さんは手先を動かすことが好きな人で、暇さえあれば洋服を作っている。この前はエルメスに行くというから、さすがマダムは行く店が違いますな、と思ったら、「スカーフを作ろうと思うんだけど、去年ウィンドウで見かけたおもしろい形のエルメスのやつを参考にするためのリサーチ」だったり。
わたしが彼らの家に週一回のお掃除人として働きに行くようになるちょっと前に、ポーセリンの絵付け講座を始めたらしく、たまに下絵や焼きを入れる前の乾かしているお皿なんかがサロンに置いてあったりした。
初期の作品は小さなものが多かったけれど、今は、貝型の大きなお皿に、うねる波をすれすれに飛ぶかもめとか、大きな丸皿に幻想的なお城とか、どんどん大作になってきている。
中でもわたしが気に入って、掃除機をかけたり戸棚を磨いたりしている間にいつも眺めていたのがこの小さなお皿。
筆先はまだ慣れておらず心もとない感じだけれど、素朴。火の鳥の赤ちゃんみたいな燃えるような羽と、首の青さがなんとも気持ちがいい。
奥さんはわたしがこのお皿を特別に気に入っているのを知っていたらしく、今日わたしを食堂に呼ぶと、お皿を包んでくれた。
「マリはいっつもこのお皿を眺めていたの知っているのよ」と、にやりとすると、「だから、あげます。ノエルのプレゼント。」
実は、バイトを止める時には思い出に譲ってもらえないかどうか聞こうと考えていた位、このお皿のことを思いつめて(!)いたので、ちょっとびっくりした。
プレゼントに一番必要な要素って、「思いがけなさ」なんじゃないかな、とふと思いました。「くるぞくるぞ」と思っているときに、期待していたものと違うものが来たりすると、ありがたいやらありがたくないやら、と途方に
暮れたりするけれど、全く予期していないときに何かを貰った時、それがたとえポストカード一枚でも嬉しくなったりするんだろうな。。。
そう考えると、クリスマスにプレゼントとか、バレンタインにチョコとかって、わかりきっているだけに難しい。
バベさんの奥さんは夏に手術をしたりして、体調があまり芳しくない。
どうぞ元気でいてください。
人生はどこにある?La vie est ailleurs ②
 先日ちらりとここで振った「La vie est ailleurs 生は彼方に
先日ちらりとここで振った「La vie est ailleurs 生は彼方に
これはミラン・クンデラというチェコの作家の小説。
この作家はフランスに移住して現在もご存命です。初めの方の作品は翻訳だけれど、今はフラ語で書いている。
本当はもう1,2冊「冗談

ちなみに、わたしが紹介した「アイデンティティは自分の中にはない」という考え方はこのクンデラのものではなく、わたしが勝手に関連付けて参考にした山田ズーニー山田ズーニー
一応、誤解のないようにお断りをしておきます。そして、クンデラの言う「La vie est ailleurs」がどういう意味なのかをお伝えできればと思います。 ※ 邦訳は読んでいません。原作を読んでのみの感想です。
私の中でカミュと夏目漱石はいわゆる「神様の位置」にいる。他にもドストエフスキーとかモーパッサンとか池波正太郎とか、この間書いたスカロンとか、まあ、好きな小説家をあげればきりがないし、まだ文学についてはほんの一部しか知らないから、毎年好きな作家は増えていく。 クンデラは、「神様の位置」に今一番近い作家だ。というと生意気ですが、この人の作品と出会えたのはかなり収穫だった。 たぶん、このひとの世界というのは文学の新しいジャンルなんじゃないかと思う。
タイトルの「La vie est ailleurs(ラ・ヴィ・エ(タ)アイヤー)」
は、邦題では「生は彼方に」と、日本語としては美しく決まっている。
けれど、この邦題はちょっとずれている様な気がしてしまう。
これは、主人公の詩人ジャロミルの生まれる直前から、たった20歳で死んでしまうまでの話。男と女の話であり、母と息子の話。 クンデラが皮肉と愛情を持って描く「詩人」という生き物は、その内情を露骨に見せる。クンデラ自体、詩人をやめて小説に転向している人だから生々しい。
「母」という生き物は、哀しくもグロテスクだと思った。
オイディプスではないけれど、親子という関係は時になんとも言えない黒い想像を生み出す。タブーと言って片付けるには、愛情があるだけにつらい。
多分、男親が娘に対して愛着を持つのと母が息子を愛するのとは種類が違うんだろう。わたしは子供を産んだことはないけれどジャロミルのお母さんの、寂しさから「息子」を「恋人」にしようとしてしまう哀しい愛情をばっさり切り捨てることはできない。けれどそれが主な原因で最愛の息子の人生はどんどん「ailleurs(別の場所)」に向かってしまう。間接的に殺してしまったと言える。矛盾。
ジャロミルの話と交錯し、最後は交わり一つになっていく文学史上実在の詩人たちの話がふわりふわりと浮かんでくるのもおもしろい。特にランボーは、なんだか今まで美しき自由奔放な少年像を勝手に想像していたのだけれど、クンデラが見せるランボーはジャロミルと混じって「ただのやばい人」だったのかも、という気を起こさせる。作家にしても、詩人にしても、芸術家は作品が評価されているから「芸術家」という称号を得ているけれど、そうでなければただの変態だと、特にフランス人作家を見ていて思う。
ジャロミルというのは「アポロン」を意味する名前で、お母さんが付けた。ジャロミルの誕生をお父さんは望んでいなかった。生まれる前からすでに、彼は一種の「片親」状態だ。お母さんはお父さんとの仲が気持ちの上でも身体の上でもすれ違い、その寂しさを埋めるために息子を溺愛する。確かにジャロミルの片言は物心つかないうちからちょっと光るものがあった。それを母は見逃さない。
ジャロミルは母によって自分より2歳年上の子供たちのクラスに入れられる。母は守護天使のようにジャロミルを守り育てるが、お陰でジャロミルは友達ができない。それで、犬を相手に遊ぶか絵を描くかするしかなくて、絵を描く技術は素晴らしいものの、どの絵も頭が犬の人間というグロテスクなものしか描けない。その後、母と旅行中にたまたま出合った絵描きに絵を習いにいくことになる。中学生のジャロミルは女性の裸に興味があって一心に彫刻を模写したりするけれど、やっぱり首から上が描けなくて、どの裸体も頭なし。
ジャロミルは自分自身の臆病と、母の愛情という名の真綿でどんどん首を絞められていく。女性に対する憧れと恐れは、自分の欲望を現実に出来ないことで彼の心に強いフラストレーションを呼び起こし、それが詩を生み出す。
こう書くとなんだか詩的な苦悩に聞こえるが、彼の最初の詩が生まれる逸話は馬鹿馬鹿しい。彼の家の下女マグダは婚約者が戦争に連れて行かれ死んでしまったことから、ずっと泣き暮らしている。その涙にほぅっとなったジャロミルは、家族がみんな出かけた夜、マグダがお風呂に入っているのをドアの鍵穴から覗く。本当はドアを開けて「いやちょっと櫛を取りに来ただけだから」と入っていこうと画策するけれど、どうしてもびびって入れない。しかも、覗いているのがマグダにバレている。ジャロミルはドアからすごすごと逃げ出すと自室にこもって爆発する。
「ああ!僕のアクアティック・アムール!」
ジャロミルの詩は「未経験」から生まれると、作品中でクンデラは解説する。彼は男らしくなりたい、いい男だと人から賞賛され愛されたい、憧れの女を抱きたい、と熱望しているけれど、どれ一つ叶わない。それが彼の心に強い感情として「一滴」にじみ出てくる。彼はそれを「おさんどんをする主婦がレモンを絞るように」搾り出す。絞り出た彼の感情は言葉になって詩に浮かび上がる。彼の詩は、彼自身の真の想いが円熟して表現された「クリスタル」のようなものになる。しかしその想いを引き出したのは「経験しなかった未熟さ」という状況。 この詩を通して、彼は自分という人間の仮面を創ろうとする。
生の自分はいけてない。だから詩を通した自分をひとが崇め愛してくれるように、詩を作る。詩を使って「自画像」の歪みを「矯正する」。こうして、彼はどんどん本当の自分を理想の自分に作り変えようとして行く。本当の自分はダメだった。けれど最後には、結局理想の自分作りも失敗していると気づく。
終盤、クンデラは「La vie est ailleurs」というせりふをジャロミル本人に、他人を批判する言葉として吐かせているが、実はそれを言っている本人がすでに本当の自分とは別の所で生きようとしてあがいているいるという皮肉がある。しかもその別の生を生きる自分もやっぱり失敗してしまう。
同時に、彼が生まれる前から、どんなに走っても彼の母からは逃れられないという宿命のようなものが、やっぱり「La vie est ailleurs」として描かれている。これはランボーと彼の母との実例がかなり効いている。 彼の詩作活動が「La vie est ailleurs」を表わしてもいる。詩の中に現れる彼のエキスとも言える強い感情は、小さな明かりの信号のように現れる。まるで彼の鼓動のように強くなったりよわくなったりしながら、そこに彼が生きているという証を放ち続ける。それ自体が「ジャロミル」というもので、いけてない実際のジャロミルから見れば、詩の中に生きるジャロミルのほうが本物に思えてしまう。そうして、彼の存在はどんどん自分の詩というテリトリーに喰われていく。
だから、「La vie est ailleurs」を、クンデラの意図に従って読み取って翻訳すると「人生は(ここにはない)、何処か別の所に」という意味になる。「彼方」は今いる場所から繋がった先の遠い場所という感覚があるけれど、「ailleurs」というのは今いる場所と同時に存在する「別」の場所、別のパラダイムという並行の感覚を、わたしは感じる。だから、少し意味がずれてしまうような気がする。日本語としてのタイトルは美しいけれど、クンデラの描く詩人の世界はシュールレアリズムの貼り絵のようなものだから、あんまりきれいに納まった感じではない。
詩人のジャック・プレヴェールは「Soleil de nuit(夜の太陽)」の扉で 言っている。
Ma vie n'est pas derrière moi ni avant ni maintenant Elle est dedans
「人生は僕の『後ろ』にあるものじゃない 『前』にあるのでも 『今』にあるのでもない それは僕の『中』にある」
ランボーは、初めて「マ・ボエーム」を読んだ時からそのイメージがタロットカードの「愚者」と重なって仕方なかったんだけど、ランボーが正位置の愚者なら、ジャロミルは逆位置なのだろう。(これはタロットカードを知らない人にはちょっとわかりにくい話。)
「中」に何かを見つけたとき、それは「人生」になるんだろうか。それとも、何かを見つけたときに「中」に人生が出来ていることに気づくのだろうか。
Ô Ciel !
 フランスに住むようになってから、パリには大体休みのたびに行っていたのだけれど、ここ1年行っていない。ので、恨みを込めてエッフェル塔から見えるパリの空。
昨日最後の試験前の試験を終えて、無事冬休みに突入。あふぇー。
フランスに住むようになってから、パリには大体休みのたびに行っていたのだけれど、ここ1年行っていない。ので、恨みを込めてエッフェル塔から見えるパリの空。
昨日最後の試験前の試験を終えて、無事冬休みに突入。あふぇー。
といっても、1月4日から二週間の中間試験だから、缶詰まって試験勉強します。万年浪人みたいだ。でも、フランスのノエルもそろそろ飽きたから特に旅行したいとも思わない。旅行するなら箱根で温泉とか沖縄とかタヒチとかがいい。
パリに行く目的はほとんどが美術館めぐり。お目当ての展示会があるからなんだけど、それ以外は予定を空けておいてパリについてから決める。というのも、大体メトロで見かけたポスターとか、たまたまテレビのニュースでやっていたのを見たとか、ラジオで聞いたとか、そういうことでふと行ってみたくなるようなものにぶつかるから。あとは、友達に芝居に誘われたりもする。映画をふらりと見たりもする。
必ず寄ってしまうところもあるけど。ピカソ美術館とか、パレ・ロワイヤルのビジュトリーとか、ヴォージュ広場とか。
ああ、現実逃避・・・一日パリに行ってこようかなあ。
今、一番行きたいところはどこだろうと自分に問うてみると、「CDG(シャルル・ド・ゴール空港」という答えが出てくる。やっぱり現実逃避。あの「出発するんです」という空気がつまって、人々が荷物を抱えてうきうきそわそわしているのがたまらなく恋しい。 さて、今日は図書館が閉まる前に、レポート用の本を借りて、クリスマスカードを書いて、チョコレートを送ったりしなければ。
« La vie est ailleurs » ①
Il ne me reste que quatre contrôles... et je me sens lourde...enrhumée...?De temps en temps, je m'égare dans cette vie entre des livres que j'entasse, lorsque je ferme le livre que je viens de finir, je sens me laisser en partie dedans. "Il faut que tu le retrouves, me dis-je, sinon tu le perdras à jamais." Mais quel MOI que dois-je donc chercher? Cet énigme me hante depuis toujours...
アイデンティティというものは、どこからくるのだろう。
それは、自分が自分の中で探さなければならないものだとずっと思っていた。 ところが、そうじゃないかもしれない。
「アイデンティティは自分の中にはない。それは人とのつながりの中にある。」
と、山田ズーニー
何かを生み出すのは辛い。 まるでもぎ取られるようにわたしは書く。
今になって、わたしはフランス語をなめていたと、思い知らされている。 フランス文学というものを打ち立てたひとりひとりの大作家たちをわたしは本当になめてかかっていた。 すんません。
と、アヴェ・プレヴォの「マノン・レスコー
ロマン・コミック
 Roman Comique
Scarron
ポール・スカロンの「ロマン・コミック」の小論文を書き上げました。
「comique (コミック)」は、本来「滑稽」という意味ではなくて「役者の」という意味。
日本語や英語だとコメディアンはお笑い系を示すけれど、フラ語では「舞台役者」という意味で使われる。もともとコメディというのも、「戯曲」という意味で使われているので、「喜劇」のみを純粋に示すとはいえない。
だからバルザックの「人間喜劇(La Comédie humaine ラ・コメディ・ユーメンヌ)」は、そういう意味では翻訳にちょっと問題がある。
バルザックが描いているのは喜劇、悲劇、表裏全てを調合した人間の世界だから、本当は「人間劇」と言ったほうが近い。
ちょっと読んだことがある人はわかると思うけれど、バルザックは喜劇よりどちらかというと悲劇と思われる一面を描いている作品が多い。死で幕が下りることが多いし、彼が生きた19世紀のフランス・ヨーロッパ社会の水面下でうごめく人々、みんなが目を向けようとしないものにも光を当てる。きれいなところも、汚いところも、へんなところも、至高の行いも、矛盾したすべてが人生だというのが「人間劇」として描かれる。
ちなみに対極に「Tragédie(悲劇)」があるので区別のために、今は「戯曲」という意味には「pièce de théâtre(ピエス・ド・テアトル)」を使います。悲喜劇(Tragi-comédieトラジ・コメディ)というジャンルもある。
スカロンの「ロマン・コミック」は、バルザックより前の時代に書かれている(第一部は1651年に出版)。「役者の」という意味の他に、「滑稽」の意味だってもちろん含めてこのタイトルをつけたのでしょうが、分類好きなフランス人は「小説(ロマン)」と「戯曲(コミック)」をあわせたこの言葉に「イロジック!(非論理的)」だと非難が紛々だったそうです。
フランス人はなにかっていうと、「論理的」とか「非論理的」というのが好きなんだが、「合理的」という人は少ない。だから後先を考えずに目の前のことに猪突猛進し、信じられないほど不器用です。「哲学」や「分析」がそれだけ国民的にできるんだったら、もうちょっとそれを実生活に生かせばいいのにと、いつも思う。
わたしの愚痴は置いておいて。
話は2部に分かれていて、2部の途中でスカロンは筆を置いたまま戻らぬ人になってしまった。3部で全てが完結するはずだったらしいというのが、残された原稿でわかる。
旅回りの劇団一行が主人公。彼ら旅芸人の生活風景、役者というものが17世紀のフランスではどういう社会的位置だったのか、芝居がどのようにして行われたのかというドキュメントにもなる描写に加えて、主人公たちの隠された姿や過去バナが語られる。スペインの小話はまるで「千夜一夜物語」のようだし、もちろん恋、決闘、手紙の行き違い、誘拐は外せない騎士道物語でもある。
そんでもって、下ネタ満載。
主人公たちは、程よくステレオタイプであり同時にオリジナリティな人々。
Le Destin ル・デスタン(「運命」という意味)
陰のある美青年。才能のある役者ながら、剣も使う騎士。隠された出生、旅芸人になるまでの過去、そして秘められた恋が徐々に明かされていきます。
La Rancune ラ・ランキュン(「恨み」)
一座の元締め的存在。いい年こいたオヤジながら、たちの悪いいたずらを止めない。人を困らせる天才。役者としては同時に王様と女王様と手下役をやってのける落語家みたいなひと。演出もし、時には戯曲も書く。
L'Étoile レトワル(「星」)
一座の花であり文字通り「スター」。美しい容姿と演技の才能に男性ファンが絶えず。表向きル・デスタンの妹となっているが、その物静かな様子、デスタンとの間の強い絆の裏には、やはり秘密が。
Ragotin ラゴタン (「Ragot(ゴシップ、おしゃべり)」から来ていると思われる)
舞台作家。途中で一座に出会い、彼らについて回る。スケープゴートのような存在でラ・ランキュンによくからかわれる。背が小さく、彼の行くところ小競り合いとパニックが耐えない。そしていつも犠牲になっておこり泣きするのはラゴタンのみ。
などなど。
フランスのル・マンの田舎の旅館やシャトーがほとんどの舞台でありながら、語られる話はイタリアだったりアフリカだったり、スペインだったり・・・。
仮面で顔を隠された婦人に恋をする男。
親に反対された結婚から逃れるため恋人と逃げようとしてムーア人に身売りされた女の子が、男装して最後はヴァレンシアの総督にまでなり、失われた恋も取り戻してしまう女。
暗闇で鉢合わせする2組のカップルが相手を取り違えたり。
騙した男を追いかけて結婚を邪魔するために活躍する女。
一人の女を忘れられない男。
明るく人情に溢れる魅力的な人々を描き、読み手に語りかけるエネルギー溢れた作者だが、実は彼は両足が麻痺しほとんど動けない状態だったという。
ファンタジックな「おとぎ話」のイメージと同時に、「コミックマシーン」ラゴタンが作り出す強烈な笑いの数々。
レトワルに横恋慕し、旅館の各部屋に置かれたおまる(昔のトイレの代わり)に足を突っ込み抜けなくなり、酔っ払って追いはぎにあい、裸で神父とシスターを追いまわしたあげく蜂の巣箱をひっくり返す。
スカロンが語り手であろうと思われるこの小説では、ナレーター自身が読み手にしょっちゅう話しかけてくる。タイトルに「あんまり気晴らしにはならない話」とか「続きを読んだらわかります」とかもよくあるし、話の途中でつっこんできたり、登場人物の名前を忘れたり。(タイムボカンシリーズの「解説しよう!」の声の人を想像してください。あんな感じ。)
さすがに17世紀にもなると、昔のフランス語になってくるので、今は使わない言葉も多い(仏日辞書がどんどん使えなくなってくる・・・。)。かなりふざけたり皮肉ったりな内容ながら、やはりレトリックは凄まじく美しい。
更に、スカロンは本当に鋭く社会を観察していて、その一員としての人々、階層の上の人も下の人も、それぞれを皮肉りながら様々な登場人物に反映させて私たちに見せる。いいやつも悪いやつも、みんなそこにいる。わたしたちの現実世界のように。
一見ただの「お話」と捉われがちな小説だけれど、芝居を通して繋がる人たちがいて、語り手が読み手を参加させようと常にこちらに気を配り、ひとつひとつの話に大勢の人がわっと登場する。
目の前に繰り広げられる様々なシーンを読んでいると、いつの間にか芝居を見ているような感覚に陥る。それが、「ロマン」と「コミック」をくっつけたスカロンの狙いだったのかもしれない。
みんなが集まって食事をするシーンもたくさん出てくるし、よく笑い、よく酔っ払う。
わたしは今、個人的なプロジェクトとして一種の「集まる」ということを実現しようとしているけれど、一体何のために人は集まるのか、というのをよく考えていた。
ミクシィもそうだと思うけれど、人々は集まりたがる。人と同じ集まりが嫌で、「自分たちは他とは違う」という方針で集まりを作るという、よくわからない状況も出てくる。
「集まる」ということが、昔からどうも苦手なわたしが集いを創るって言うのは不可能じゃないのか?とも思う。何しろ、「集団トイレ(女の子の友達同士が必ず一緒にトイレに行かなくてはならないという謎の掟)」がどうしても出来ない中学生だったから、集い下手キャリアは長い。今の中学生はそんなことしないのかな。
集まる目的が、寂しいからということ。
自分に注目して欲しいからということ。
そういうものを抱えながらも、それを超えたつながりを創る集まりは、スカロンが描く「コミック」な人々のように、力強く、温かいんだろうと思う。
Roman Comique
Scarron
ポール・スカロンの「ロマン・コミック」の小論文を書き上げました。
「comique (コミック)」は、本来「滑稽」という意味ではなくて「役者の」という意味。
日本語や英語だとコメディアンはお笑い系を示すけれど、フラ語では「舞台役者」という意味で使われる。もともとコメディというのも、「戯曲」という意味で使われているので、「喜劇」のみを純粋に示すとはいえない。
だからバルザックの「人間喜劇(La Comédie humaine ラ・コメディ・ユーメンヌ)」は、そういう意味では翻訳にちょっと問題がある。
バルザックが描いているのは喜劇、悲劇、表裏全てを調合した人間の世界だから、本当は「人間劇」と言ったほうが近い。
ちょっと読んだことがある人はわかると思うけれど、バルザックは喜劇よりどちらかというと悲劇と思われる一面を描いている作品が多い。死で幕が下りることが多いし、彼が生きた19世紀のフランス・ヨーロッパ社会の水面下でうごめく人々、みんなが目を向けようとしないものにも光を当てる。きれいなところも、汚いところも、へんなところも、至高の行いも、矛盾したすべてが人生だというのが「人間劇」として描かれる。
ちなみに対極に「Tragédie(悲劇)」があるので区別のために、今は「戯曲」という意味には「pièce de théâtre(ピエス・ド・テアトル)」を使います。悲喜劇(Tragi-comédieトラジ・コメディ)というジャンルもある。
スカロンの「ロマン・コミック」は、バルザックより前の時代に書かれている(第一部は1651年に出版)。「役者の」という意味の他に、「滑稽」の意味だってもちろん含めてこのタイトルをつけたのでしょうが、分類好きなフランス人は「小説(ロマン)」と「戯曲(コミック)」をあわせたこの言葉に「イロジック!(非論理的)」だと非難が紛々だったそうです。
フランス人はなにかっていうと、「論理的」とか「非論理的」というのが好きなんだが、「合理的」という人は少ない。だから後先を考えずに目の前のことに猪突猛進し、信じられないほど不器用です。「哲学」や「分析」がそれだけ国民的にできるんだったら、もうちょっとそれを実生活に生かせばいいのにと、いつも思う。
わたしの愚痴は置いておいて。
話は2部に分かれていて、2部の途中でスカロンは筆を置いたまま戻らぬ人になってしまった。3部で全てが完結するはずだったらしいというのが、残された原稿でわかる。
旅回りの劇団一行が主人公。彼ら旅芸人の生活風景、役者というものが17世紀のフランスではどういう社会的位置だったのか、芝居がどのようにして行われたのかというドキュメントにもなる描写に加えて、主人公たちの隠された姿や過去バナが語られる。スペインの小話はまるで「千夜一夜物語」のようだし、もちろん恋、決闘、手紙の行き違い、誘拐は外せない騎士道物語でもある。
そんでもって、下ネタ満載。
主人公たちは、程よくステレオタイプであり同時にオリジナリティな人々。
Le Destin ル・デスタン(「運命」という意味)
陰のある美青年。才能のある役者ながら、剣も使う騎士。隠された出生、旅芸人になるまでの過去、そして秘められた恋が徐々に明かされていきます。
La Rancune ラ・ランキュン(「恨み」)
一座の元締め的存在。いい年こいたオヤジながら、たちの悪いいたずらを止めない。人を困らせる天才。役者としては同時に王様と女王様と手下役をやってのける落語家みたいなひと。演出もし、時には戯曲も書く。
L'Étoile レトワル(「星」)
一座の花であり文字通り「スター」。美しい容姿と演技の才能に男性ファンが絶えず。表向きル・デスタンの妹となっているが、その物静かな様子、デスタンとの間の強い絆の裏には、やはり秘密が。
Ragotin ラゴタン (「Ragot(ゴシップ、おしゃべり)」から来ていると思われる)
舞台作家。途中で一座に出会い、彼らについて回る。スケープゴートのような存在でラ・ランキュンによくからかわれる。背が小さく、彼の行くところ小競り合いとパニックが耐えない。そしていつも犠牲になっておこり泣きするのはラゴタンのみ。
などなど。
フランスのル・マンの田舎の旅館やシャトーがほとんどの舞台でありながら、語られる話はイタリアだったりアフリカだったり、スペインだったり・・・。
仮面で顔を隠された婦人に恋をする男。
親に反対された結婚から逃れるため恋人と逃げようとしてムーア人に身売りされた女の子が、男装して最後はヴァレンシアの総督にまでなり、失われた恋も取り戻してしまう女。
暗闇で鉢合わせする2組のカップルが相手を取り違えたり。
騙した男を追いかけて結婚を邪魔するために活躍する女。
一人の女を忘れられない男。
明るく人情に溢れる魅力的な人々を描き、読み手に語りかけるエネルギー溢れた作者だが、実は彼は両足が麻痺しほとんど動けない状態だったという。
ファンタジックな「おとぎ話」のイメージと同時に、「コミックマシーン」ラゴタンが作り出す強烈な笑いの数々。
レトワルに横恋慕し、旅館の各部屋に置かれたおまる(昔のトイレの代わり)に足を突っ込み抜けなくなり、酔っ払って追いはぎにあい、裸で神父とシスターを追いまわしたあげく蜂の巣箱をひっくり返す。
スカロンが語り手であろうと思われるこの小説では、ナレーター自身が読み手にしょっちゅう話しかけてくる。タイトルに「あんまり気晴らしにはならない話」とか「続きを読んだらわかります」とかもよくあるし、話の途中でつっこんできたり、登場人物の名前を忘れたり。(タイムボカンシリーズの「解説しよう!」の声の人を想像してください。あんな感じ。)
さすがに17世紀にもなると、昔のフランス語になってくるので、今は使わない言葉も多い(仏日辞書がどんどん使えなくなってくる・・・。)。かなりふざけたり皮肉ったりな内容ながら、やはりレトリックは凄まじく美しい。
更に、スカロンは本当に鋭く社会を観察していて、その一員としての人々、階層の上の人も下の人も、それぞれを皮肉りながら様々な登場人物に反映させて私たちに見せる。いいやつも悪いやつも、みんなそこにいる。わたしたちの現実世界のように。
一見ただの「お話」と捉われがちな小説だけれど、芝居を通して繋がる人たちがいて、語り手が読み手を参加させようと常にこちらに気を配り、ひとつひとつの話に大勢の人がわっと登場する。
目の前に繰り広げられる様々なシーンを読んでいると、いつの間にか芝居を見ているような感覚に陥る。それが、「ロマン」と「コミック」をくっつけたスカロンの狙いだったのかもしれない。
みんなが集まって食事をするシーンもたくさん出てくるし、よく笑い、よく酔っ払う。
わたしは今、個人的なプロジェクトとして一種の「集まる」ということを実現しようとしているけれど、一体何のために人は集まるのか、というのをよく考えていた。
ミクシィもそうだと思うけれど、人々は集まりたがる。人と同じ集まりが嫌で、「自分たちは他とは違う」という方針で集まりを作るという、よくわからない状況も出てくる。
「集まる」ということが、昔からどうも苦手なわたしが集いを創るって言うのは不可能じゃないのか?とも思う。何しろ、「集団トイレ(女の子の友達同士が必ず一緒にトイレに行かなくてはならないという謎の掟)」がどうしても出来ない中学生だったから、集い下手キャリアは長い。今の中学生はそんなことしないのかな。
集まる目的が、寂しいからということ。
自分に注目して欲しいからということ。
そういうものを抱えながらも、それを超えたつながりを創る集まりは、スカロンが描く「コミック」な人々のように、力強く、温かいんだろうと思う。
ラルゴ
 PIANO PIANO...CHI VA PIANO VA SANO... CHI VA SANO VA LONTANO....................
「祭り」のあと、あなたは誰を思う?
PIANO PIANO...CHI VA PIANO VA SANO... CHI VA SANO VA LONTANO....................
「祭り」のあと、あなたは誰を思う?
"PROVERBE ITALIEN qui veut dire : LENTEMENT LENTEMENT.... QUI VA LENTEMENT VA SÛREMENT.. QUI VA SÛREMENT VA LONGTEMPS... ou un proverbe français QUI VA LOIN MÉNAGE SA MONTURE . Économisez vos forces pour durer le plus longtemps possible tout en restant efficace." 英語のスピーチの準備が終わらず朝の6時までかかったという私に、いつもお世話になっていてフランスの祖父のような存在(彼はわたしを「娘のような」というが)のバベ氏がくれたメールの言葉だ。 「イタリアのことわざでこういうのがあります: 『ゆっくりと、ゆっくりと・・・ゆっくりはしっかり・・・しっかり進む者は長続きするよ・・・』 または、フランスでこういうことも言います: 『遠くへ向かう者は己の馬をいたわる』 常に最高に、そして出来るだけ息の長い力を発揮できるように、セーブして行きなさい。」 英会話を始めたのは小学校3年生の時だった。オーストラリア人やアメリカ人のあんちゃんたちと犬のように転げ周り、おしゃべりを止めないから「スピーカー」とあだ名されながら、わたしは英会話教室が楽しくて楽しくて仕方なかった。 英語自体にはそんなに興味がわかなかったけれど、お陰でガイジンに対する変な恐怖感はまったく私の中に生まれなかった。 高校まで英会話は続けたけど、あまり上達はしなかった。それから10年もたって、フランスの大学で英語にうなされるとは思いもしなかったぜ・・・。 そして、去年1年の時の英語の成績を知っていながら、わたしに日本文学と英文学におけるファンタジック・ヒーローの比較についてのスピーチをさせるマダム・スリニャックも、かなりの冒険野郎だと思う。 さて、テーマにしたのは宮沢賢治。銀河鉄道の夜はあんまり好きじゃなかったんだけど、授業で取り上げた「アリス」や「ピーターパン」などの不思議の国で活躍する子供に匹敵するジョバンニを中心にした。19世紀の日本文学ではこういうタイプのヒーローを見つけようとするとなかなか難しい。 「南総里見八犬伝は?」というナイスな友人の案を取りたかったが、ヒーローが子供じゃないんだよねぇ・・・。 賢治といえば、「注文の多い料理店」が大好きだった。絵本をぞくぞくしながら何度も読んだ。「雪わたり」の「きっくとん、きっくとん、きっくとんとん」という言葉のリズムも好きだった。 ちくま文庫からでているロジェ・パルヴァースの英訳をたまたま見つけたのだけれど、彼が翻訳を始めたのは日本語の訓練をするためだったというのが興味深かった。 賢治の様々な面を紹介しているサイトを調べてやっと40分ほどの原稿に仕上げたら、朝6時だったわけだ。 自分の脳みそから全て出た言葉ではないから、原稿を読んでも聞いている人たちの思考の上を滑っていくだけだとわかっていた。だから、とにかく、なんとか自分で感じ、その場でめちゃくちゃでもいいから生の言葉を伝えるしかないと思っていた。 絵本を見せるのも一つの手にした。 スピーチの目的は、「へえ、日本の文学にもこういうのがあるんだ、おもしろそうだな」という生徒を一人でもゲットできたらよしとした。 結果は成功した。 授業のあと、数人のフランス人生徒から囲まれて、話の続きはどうなるのか、銀河鉄道はどっからきたのか、と質問された。 こんな風に接してきた人たちは初めてだった。 次の授業を待っている間に、別の女の子が一人話しかけてきた。 「あなたのスピーチすごかった!日本語とフランス語を話せるだけでも、すでにすごいのに、更にもう一ヶ国語も使いこなせるなんて、いいなあ!」 それは誤解です。 わたしは、英語が本当に「nul(下手っぴ)」だと言った。謙遜とかではなくて、去年の成績だってとんでもなかった。 試験は大体がテキストの抜粋の説明なんだけれど、フランス風のきちんとした枠組みに従って英語で説明をつけていかなければならず、やったことのなかったわたしは何を書いていいかわからなかった。 という話をしたら、彼女は「わたしが図書館で見つけた説明文の構成の仕方の本があるんだけど、それをシートにしたのがあるの」とカラフルにパソコンで打ち直された紙を一枚ひらりとだし、「はい」とわたしにくれた。 「わあ、ありがと。じゃあ、コピーして返すね」といったら、「ううん、パソコンに原稿残っているからいいの、あげる」とにっこりした。 「・・・!!!」 この話を、日本の友人に話したら、彼女は即座にこう言った。 「いいものをね、貰ったら、お返しがしたくなるんだよね、人は。 彼女はまりのスピーチを聞いて、何かを受け取ったんだよ。それがうれしくて、お返しがしたかったんだよ。」 彼女は女優だ。ダンスもすれば演出もする。わたしが大好きな役者だ。 やはり、そういうことを知っていたから彼女のやるもの、彼女がわたしに紹介する人々はみんなあったかいんだなと思った。 スピーチの終わった直後は暫く「お前はナニジンだ」という謎のミックス語しか話せなかった。旅行でもしない限りまともに英語で話も出来ないのに、40分もスピーチをした後遺症はひどい。でも、これで少し脳みそが活性化されたかもしれない。 徹夜して、へんなボルテージが上がったまま、コーヒーしか入れていないおなかはいつものように催促もしない。 放心した頭をかかえながら、思いも寄らない喜びを英語のクラスの人たちから貰って、余韻の中でわたしはゆらゆらしていた。 久しぶりに身体を使って「表現」をしたなあ、と思った。役者だったときの感覚が目覚めているのがわかる。役者と乞食は3日やったら辞められないというけれど、この「祭り」の爆発を味わったことがある人は、ふむふむとこの言葉にうなずくんだろうな。 そうして、それが静まった時、ふと思い出す顔がある。 飲み会のあとでも、コンサートのあとでも、 わっと感情が高まった後のしんとした静けさの中で、 一番先に、ああ、このあったかい波のようなものを伝えたいな、と思う人が、あなたにもいるだろう。 それが、あなたが一番想いをかけている人だと思う。
Père Noël est un...
サンタさんへ。今より3倍能率のいい脳みそがほしいです。 まりより。 あんまりいい子じゃないから、今年は来てくれないかもしれない・・・などと心配する29歳。
LE POURQUOI
「なぜ」がないと、弱い。話をするにも、 話を聞くにも、 書くのも、 行動するのも、 理解をするためにも、 「なぜ」は必要。 ここのところ、ずっとひっかかっていたある人の言葉 : 「なぜ、僕のことがいいとみんなが言うのか、わからない。」 彼は、プロの「表現者」。 つまり「彼はいい」とか「彼はよくない」とか、常に、あからさまに人から評価されるシチュエーションにいる。 彼は決して自惚れの境地で調子をこいてこんなせりふを口にしたわけではない。本当にわからずに、心の底から絞り出た疑問のようだった。 初めはその言葉をどう捉えていいかわからなかった。 わたしが彼を「いい」と思えないわけではない。 なのに「これだ!」という答えがない。「好きな理由」というのが、何を言っても通り一遍の薄っぺらなものに聞こえて、言えば言うほど彼のことを貶めていくような、よくわからない悪循環に陥った。 何をどんな風に言ったって、彼は納得しないんだと気づく。でもまてよ、その前に、この質問はするべきものなのかな? 例えば、好きな人に大決心して、面と向かって告白したとします。 相手に「なんで?なんで僕(または私)なの?」と聞かれたら、 「いや、それはその、つまり・・・や、やさしいし・・・」 と、急に言葉がはっきりしなくなったりしないでしょうか。 すきすきすきすき!というピンク色のスパイラルを切り裂く青い「なんで?」。 これは、しちゃいけない質問で、答えちゃいけない質問なんじゃないのか? フラ語で「ジュテーム(きみをあいしてる)」と言うけれど、 これは真剣な愛の告白の時のみの呪文で、形容する余計なものをつけてはならない。 ① Je t'aime. 私はきみを愛しています。 ② Je t'aime beaucoup. 私はきみをとても好きです。 一見「とても」をつけたほうが熱意が伝わりそうだけれど、 ①は恋愛対象 ②は友達でいましょう なぜかという理由を恩師K氏(フランス人)に聞いたところ、 「愛は本来無限であるべきものという観念がある。形容するものをつけると、愛に一定の限界を作ってしまうことになるから、自分の愛する気持ちも限定されてしまう。」 浮いた噂のなさそうなおっさんから、こういう熱い説明を聞くとちょっと胸がじぃんとしたものでした。 Je ferme la parenthèse.(「カッコを閉じます」大学の先生たちは「もとい」という意味でよくこう言う。) なんで彼はこんな質問をするのだろう。 他の「プロフェッショナル」と言われるひとは、こういうことを考えたりするのだろうか? 「なぜ人は自分をいいというのか?」は、逆に言えば、 「自分は人に何をいいと言わせるのか?」つまり、 「自分は人(お客さん)に、何を提供するのか?」 そうか、彼は、自分のアイデンティティを探していたんだ。 それは彼にしか見つけられない。他の人がそれに色をつけていくことはできる。けれど、色をつけるべきものがなければ、いくら絵の具をたくさん持っていてもどうしようもない。 だけど、それを一緒に探していくことはできるよなあ。 わたしはどうだろう?わたしは、わたしのやりたいことを通して一体何を人に提供するのだろうか・・・。 主語を自分に置き換えると、他人事も自分の事になる。 「なぜ」が問える時、相手も自分も一緒に深くなって行く。
Adieu
久しぶりに、会った。いつものように、わたしに色々と質問する。 いつものように、壁に背中をもたれて、 手を後ろにまわして。 相変わらず忙しそうだった。 「じゃあ」と、今日はわたしから言った。 一度も言えなかった、「じゃあ」。 いつも彼が切り出す「じゃあ」に、ずたずたに切り裂かれるような気がしていた。 「A la prochaine fois,(またね)」 ふと、思いも寄らない言葉がするりと出た。 「...ou plus jamais(...それか、もうこれが最後かもね)」 彼は、ちょっと目を丸くして、それからにやりとすると、 「じゃ、Adieu(アデュウ)だね」 と、言った。 「うん、Adieu(アデュウ)。」 そうか、アデュウという言葉は、「神の元へ」という言葉だったんだ、だから、もう二度と会わないときに言うんだと、初めて気がついた。 これからも、彼とは会うかもしれないけれど、 わたしの想いは、Adieuだった。 まるでわたしの意識を裏切って細胞から出たような言葉だった。 わたしの身体が、区切りを欲していたんだ。 これでいい。 これで、いい。
神仕掛けの機械
Deus ex machinaデウセクスマキナ。 Deus ex machina デウス エクス マキナ 神 ~による マシーン 直訳すると、「神仕掛けの機械」 またラテン語かとおっしゃらずに。 ラテン語を知らずとも、オデュッセー、イーリアスを読んだことがあれば出くわす言葉です。 (これをジャン・コクトーは「Machine infernale(マシーン・アンフェルナル)」と見事に言い表し戯曲にした。 邦題「地獄の機械」は、あまりいけてないと思う。確かにこのフランス語を訳すのは難しい。ドラえもんのひみつ道具的に言えば 「地獄作り出し機~!」というのが一番ふさわしいのだけれど、それではジャン様は許してくれまい。) デウセクスマキナとは、オリンポスの神々による人間の運命への介入という意味。神様たちは、自分たちの機嫌によって人間にそっぽを向いたり微笑んだり、あっけらかんと人間の生死を決定する。 冒頭からずっと引っ張り続ける「アキレウスの怒り」、ユリシーズの放浪、トロイの陥落、みんな元はといえば女神さま同士の究極の美人争いが原因。人間の倫理とか義理人情とか熱く語られるのだけれど、神様が「やっぱ、もうアイツの味方すんのやーめた」と言えば終了。 人生で、どう考えてもなんかよくわからん力がわたしの思考をストップさせ、どこかに導いているとしか思えないという時がある。そんな時、わたしはこの言葉を思い出す。 今年の大学の授業のオプション選択で「コミュニケーション科学」を選んだのは、わたしにとってはデウセクスマキナだった。 わたしのいるナント大学は3年間の教育プログラム中、2年からは三つの進路に分かれる。現代文学コース、演劇コース、コミュニケーション科学コース。わたしは現代文学コースなのだが、これが一番オプションが多彩で、本来よそのコース専門のものでも参加できる。 1年の最初の集会で、それぞれのコースの説明とオプションの先生の紹介があった。コミュニケーション科学担当の先生はもっさりしてめがねをかけ、いかにも「メディアコメンテーター(なんだそりゃ)」といった風体。話し方、授業の内容、外見を総合してわたしの中では「却下」だった。 ところが2年の初めの登録で、うっかり彼のオプションを取ってしまった。 どうしたことだ。 授業のテーマに唆されたかもしれない。 「Histoire de l'écriture et de la mise en page」 文字とレイアウトの歴史。 授業に行ってみたら大歓迎された。日本人だかららしい。 授業は3時間ぶっ通しなのだが、まさにマルチな造詣の深さを持ち、言葉の端々に遊びをちりばめ、わたしたち生徒を「mes petits amis(わが友)」と呼ぶコルメレ先生の授業は非常に為になる。 そうして、とても大事だなと思ったのは、教える「目的」があるということだ。彼の場合は「生徒が何かを掴む」ために情熱を持って教えている先生だと生徒に伝わってくる。 「教える」は教師というタイトルを持つ人全てに共通する最低限の活動になる。違いは、「教える」を修飾するものに現れる。 「なぜ」教えるのか。「なぜ」の部分にそれぞれの教師の根本的なところが現れる。大学の先生は、インテリなだけで「なぜ」の中に「生徒を導く」という教育には欠かせないキーワードを全く持たない先生がたくさんいる。そういう人にとって、生徒はただのナンバーになってしまう。 明日はフランスのお盆トゥッサン。菊をお供えし、家族で集まる祝日。すでに人の姿は稀で街はしん、としている。 コルメレ先生は、言う。 「明日はじいちゃんばあちゃん、先祖のことを考えなさい!」 ヘブライ語とギリシャ語の発達の違いについて説明しながら、言う。 「レクチャーとは筆者が閉じ込めた言葉を解き放つ行為である。」 いい先生に出会えた神様の介入は、Machine paradisiaque(天国作り出し機)だった。
そもそもの話
このブログを記していく上で、「こころ」というものにもっと丁寧に向き合おうと思うようになったひとつのキーワードがある。それが、「Vis comica(ヴィス・コミカ)」 Vis comicaとはラテン語で、直訳すると「喜劇の力」。 わたしはこれを「笑いの力」と訳します。 わたしがこの言葉に反応したのには、まったく縁のないように見える二つのきっかけがある。 ひとつは、今わたしが学んでいる仏文。フランス文学は、やってみるまで美しく気取ったイメージしかなかったんだけれど、実際に生でぶつかってみると、こんなに「笑い」に知性を費やし、くだらないことに情熱をかけている、素晴らしいものだとわかった。 それを、祖先の古代ローマの人はすでに「笑いの力」として知っていた。 もうひとつは、落語。 落語を聴き始めて2ヶ月になる。知れば知るほど、なんだかよくわからない深みにはまるようだけれど、それでもいいんじゃないかとだらだら思う。 普段わたしたちは人を笑わせ、人と笑い合う力を持っている。 それは人の心を温め、動かす大きなエネルギー。 人生には、ちょっとがんばらないといけない場面がたくさんあります。 思うとおりに行かなかったり 誤解されたり 傷つけてしまったり 悲しい思いをしたり こんがらがってしまったり 離れてしまったり そんな時、落語の持つ「笑いの力」に助けられた。 笑う時、人には明かりが灯るような気がする。 小さくても、ぽうっと明かりがつけば、自分の周りに誰かがいるということがわかる。それは、繋がりを見つけるということ。 自分がどこにいるのか見失ってしまった時、 自分の明かりを頼りに出来ればいい。 そしてそれが、誰かの道しるべになったらいい。 わたしが、誰かの明かりに助けられるように。











